| 品番 | 内容 | 演奏者 |
|---|---|---|
| COLIN CURRIE RECORDS CCR-0001 |
スティーヴ・ライヒ:ドラミング(1971) | コリン・カリー・グループ〔コリン・カリー、ジョージ・バートン、アントワーヌ・ブデヴィ、リチャード・ベンヤフィールド、アダム・クリフォード、オーウェン・ガンネル、キャサリーン・リング、アドリアン・スピレット、サム・ウォルトン〕 ロウランド・サザーランド(ピッコロ) シナジー・ヴォーカルズ〔ミカエラ・ハスラム、ヒザー・ケアンクロス(口笛も担当)〕 録音:2017年5月8日、ロンドン、倉庫にて(24bit 96kHz PCM) |
|
||
| CCR-0002 |
THE SCENE OF THE CRIME アンドレ・ジョリヴェ:エプタード(1971)[パーカッション&トランペット] ジョー・ダデル(b.1972):キャッチ[マリンバ&トランペット] トビアス・ブロストレム(b.1978):ドリーム・ヴァリエーションズ[パーカッション(ゴング、ヴィブラフォン他)&トランペット] ダニエル・ベルツ(b.1943):ディアロゴ4[パーカッション&トランペット] ブレット・ディーン:シーン・オブ・ザ・クライム(2017)[トランペット、フリューゲルホルン&パーカッション] |
コリン・カリー(パーカッション) ホーカン・ハーデンベルガー(Tp) 録音:2018年6月9-11日、ポットン・ホール |
|
||
| CCR-0003 |
コリン・カリー&スティーヴ・ライヒ~ライブ・アット・フォンダシオン・ルイ・ヴィトン クラッピング・ミュージック(1972) Proverb(ヴィトゲンシュタインの‘警句’)(1995) マレット四重奏曲(2009) パルス(2015) 木片のための音楽(1973) |
コリン・カリー、スティーヴ・ライヒ コリン・カリー・グループ、 シナジー・ヴォーカルズ 録音:2017年12月、パリ(ライヴ) |
|
||
| CCR-0004 KKC-6342 国内盤仕様 税込定価 |
ハインツ・カール・グルーバー:打楽器協奏曲集 (1)ROUGH MUSIC (2)INTO THE OPEN... |
コリン・カリー(打楽器独奏) (1)ファンホ・メナ(指) (2)ヨン・ストゥールゴールズ(指) BBCフィルハーモニック 録音:(1)2013年12月6日マンチェスター、ブリッジ・ウォーター・ホール (2)2015年7月20日ロンドン、ロイヤル・アルバート・ホール(BBCプロムスでの世界初演) |
|
||
| LSO-0001 |
ドヴォルザーク:交響曲第9番「新世界より」 | コリン・デイヴィス(指)LSO 録音:1999年9月29日&30日バービカン・センター・ライヴ |
| LSO-0002 |
ドヴォルザーク:交響曲第8番「イギリス」 | コリン・デイヴィス(指)LSO 録音:1999年10月3日&4日バービカン・センター・ライヴ |
| LSO-0003(2CD) |
ベルリオーズ:劇的交響曲「ロメオとジュリエット」 | ダニエラ・バルチェローナ(Ms)、 ケネス・ターヴァー(T)、 オルラン・アナスタソフ(Bs)、 コリン・デイヴィス(指)LSO&cho 録音:2000年1月11日&13日バービカン・センター・ライヴ |
| LSO-0004(2CD) |
ベルリオーズ:歌劇「ベアトリスとベネディクト」 | エンケレイダ・シュコサ(Ms;ベアトリス) ケネス・ターヴァー(T;ベネディクト) スーザン・グリットン(S;エロ)、サラ・ミンガルド(A;ウルシュラ)、 ロラン・ナウリ(B;クラウディオ)、 デイヴィッド・ウィルソン=ジョンソン(Br;ソマローヌ)、 ディーン・ロビンソン(B;ドン・ペドロ)、 コリン・デイヴィス(指)LSO&cho 録音:2000年6月6日&8日バービカン・センター・ライヴ |
| LSO-0005 |
ブラームス:ドイツ・レクイエム | ハロリン・ブラックウェル(S) デイヴィッド・ウィルソン=ジョンソン(Br) アンドレ・プレヴィン(指)LSO&cho 録音:2000年6月17日&18日バービカン・センター・ライヴ |
| LSO-0007 |
ベルリオーズ:幻想交響曲*、 「ベアトリスとベネディクト」序曲+ |
コリン・デイヴィス(指)LSO 録音:2000年9月27日&28日*、2000年6月6日&8日+バービカン・センター |
| LSO-0008(2CD) |
ベルリオーズ:劇的物語「ファウストの劫罰」 | エンケレイダ・シュコサ(Ms;マルゲリータ) ジュゼッペ・サバティーニ(T;ファウスト)ミシェル・ペルテュージ(Br;メフィストフェレス) デイヴィッド・ウィルソン=ジョンソン(Br;ブランデル) コリン・デイヴィス(指)LSO&cho 録音:2000年10月15日&17日バービカン・センター |
| LSO-0010(4CD) |
ベルリオーズ:歌劇「トロイアの人々」 | ベン・ヘプナー(T;エネー) ミシェル・ドゥユング(Ms;ディドン) ペトラ・ラング(Ms;カサンドラ、カサンドラの幽霊) サラ・ミンガルド(A;アンナ) ペテル・マッテイ(Br;コレブ、コレブの幽霊) スティーヴン・ミリング(B;ナルバル) ケネス・ターヴァー(T;イオパス) トビー・スペンス(T;イラス) オルリン・アナスタソフ(B;エクトルの影) ティグラン・マルティロシアン(B;パンテー) イサベル・カルス(Ms;アスカーニュ) アラン・ユーイング(B;プリアム、プリアムの幽霊)、他 コリン・デイヴィス(指)LSO&cho 録音:2000年11月30日~12月9日バービカン・センター |
| LSO-0014 |
ドヴォルザーク:交響曲第7番 | コリン・デイヴィス(指)LSO 録音:2001年3月21日バービカン・センター |
| LSO-0017 |
エルガー:交響曲第1番 | コリン・デイヴィス(指)LSO 録音:2001年9月30日&10月1日バービカン・センター |
| LSO-0018 |
エルガー:交響曲第2番 | コリン・デイヴィス(指)LSO 録音:2001年10月3日&4日バービカン・センター |
| LSO-0019 |
エルガー:交響曲第3番(エルガーによるスケッチに基づくアンソニー・ペインによる完成版) | コリン・デイヴィス(指)LSO 録音:2001年12月13日&14日バービカン・センター |
| LSO-0022 |
ブルックナー:交響曲第6番 | コリン・デイヴィス(指)LSO 録音:2002年2月19日&20日バービカン・センター |
| LSO-0023 |
ブルックナー:交響曲第9番 | コリン・デイヴィス(指)LSO 録音:2002年2月22日&24日バービカン・センター |
| LSO-0029 |
ホルスト:組曲「惑星」 | コリン・デイヴィス(指)LSO、同女声cho 録音:2002年6月バービカン・センター |
| LSO-0030 LSO-0535(1SACD) |
ショスタコーヴィチ:交響曲第11番「1905年」 | ムスティスラフ・ロストロポーヴィチ(指)LSO 録音:2002年3月19日&20日バービカン・センター |
| LSO-0037 |
シベリウス:交響曲第5番*、第6番+ | コリン・デイヴィス(指)LSO 録音:2003年12月10-11日*、2002年9月28-29日+ |
| LSO-0038(2CD) |
マーラー:交響曲第6番「悲劇的」 | マリス・ヤンソンス(指)LSO 録音:2002年11月27日&28日、ロンドン |
| LSO-0040 |
ベルリオーズ:交響曲「イタリアのハロルド」 | タベア・ツィマーマン(Va) コリン・デイヴィス(指)LSO 録音:2003年2月16日~27日・ライヴ |
| LSO-0043 |
ブラームス:交響曲第2番、二重協奏曲* | ゴルダン・ニコリッチ(Vn) ティム・ヒュー(Vc) ベルナルド・ハイティンク(指)LSO 録音:2003年5月17日&18日バービカン・センター |
| LSO-0045 |
ブラームス:交響曲第1番、悲劇的序曲 | ベルナルド・ハイティンク(指)LSO 録音:2003年5月22日&23日、ロンドン |
| LSO-0046(12CD) ★ |
ベルリオーズ・エディション 劇的交響曲「ロメオとジュリエット」 歌劇「ベアトリスとベネディクト」 幻想交響曲 歌劇「ベアトリスとベネディクト」序曲 劇的物語「ファウストの劫罰」 歌劇「トロイアの人々」 交響曲「イタリアのハロルド」 |
コリン・デイヴィス(指)LSO ※LSO-0003、LSO-0004、LSO-0007、LSO-0008、LSO-0010、LSO-0040のセット化 |
| LSO-0051 LSO-0552(1SACD) |
シベリウス:交響曲第3番*、第7番# | コリン・デイヴィス(指)LSO 録音:2003年10月1日&2日*、2003年9月24日&25日# |
| LSO-0054(3CD) |
ブリテン:歌劇「ピーター・グライムズ」 | グレン・ウィンスレード(ピーター・グライムズ) ジャニス・ワトソン(エレン・オーフォード) アントニー・マイケルズ=ムーア(ボルストロード船長) キャサリン・ウィン=ロジャース(セドリー夫人)ジェイムズ・ラザフォード(スワロー)、他 コリン・デイヴィス(指)LSO&cho 録音:2004年1月10日&12日バービカン・センター |
| LSO-0055(2CD) LSO-0528(2SACD) |
ヴェルディ:歌劇「ファルスタッフ」 (演奏会形式) |
ミケーレ・ペルトゥージ(ファルスタッフ) カルロス・アルバレス(フォード) ビューレント・ベツデューツ(フェントン) アラスデア・エリオット(カイウス) ペーター・ホアレ(バルドルフォ) ダレン・ジェフリー(ピストラ) アナ・イバッラ(フォード夫人アリーチェ) マリア・ホセ(ナンネッタ) マリーナ・ドマシェンコ(ページ夫人メグ) コリン・デイヴィス(指)LSO 録音:2004年5月17、20、23日・ライヴ |
| LSO-0056 LSO-0544(1SACD) |
ブラームス:交響曲第3番ヘ長調*、セレナード第2番+ | ベルナルド・ハイティンク(指)LSO 録音:2004年6月16-17日ライヴ*、2003年5月21-22日ライヴ+ |
| LSO-0057 LSO-0547(1SACD) |
ブラームス:交響曲第4番 | ベルナルド・ハイティンク(指)LSO 録音:2004年6月16-17日バービカン・ホール |
| LSO-0058 LSO-0550(1SACD) |
ショスタコーヴィチ:交響曲第5番 | ムスティスラフ・ロストロポーヴィチ(指)LSO 録音:2004年7月7日&8日バービカン・センター |
| LSO-0059 LSO-0526(1SACD) |
ドヴォルザーク:交響曲第6番 | コリン・デイヴィス(指)LSO 録音:2004年9月28日&29日バービカン・センター |
| LSO-0060 LSO-0527(1SACD) |
ショスタコーヴィチ:交響曲第8番 | ムスティスラフ・ロストロポーヴィチ(指)LSO 録音:2004年11月3-4日バービカン・センター |
| LSO-0061 |
スメタナ:連作交響詩「わが祖国」 | コリン・デイヴィス(指)LSO 録音:2004年10月10、15日バービカンホール・ライヴ(拍手なし) |
|
||
| LSO-0070(4CD) ★ |
ブラームス:交響曲全集 交響曲第1番*、悲劇的序曲+ 交響曲第2番#、二重協奏曲# 交響曲第3番**、セレナード第2番++ 交響曲第4番## |
ベルナルド・ハイティンク(指)LSO 録音:2003年5月21日*、2003年5月17日+、2003年5月17日#、2004年6月16-17日**、2003年5月21-22日++、2004年6月16-17日## |
| LSO-0071(3CD) ★ |
ドヴォルザーク:交響曲第6番*、 第7番+、第8番#、第9番** |
コリン・デイヴィス(指)LSO 録音:1999年9月29-30日**、1999年10月3-4日#、2001年3月21日+、2004年9月28-29日* |
| LSO-0072(3CD) ★ |
エルガー:交響曲第1番*、第2番+、 第3番(A.ペイン補筆)# |
コリン・デイヴィス(指)LSO 録音:2001年9月30日-10月1日*、2001年10月3-4日+、2001年12月13-14日# |
| LSO-0074 LSO-0574(1SACD) |
シベリウス:クレルヴォ交響曲 | ペーテル・マッティ(Br)、モニカ・グロープ(Ms)、 サー・コリン・デイヴィス(指)LSO&ロンドン響男声cho 録音:2005年9月18日&10月9日ロンドン、バービカンセンター(ライヴ) |
|
||
| LSO-0076 LSO-0576(1SACD) |
ウォルトン:交響曲第1番 | サー・コリン・デイヴィス(指)LSO 録音:2005年9月23日&12月4日ロンドン、バービカンセンター(ライヴ) |
|
||
| LSO-0078 LSO-0578(1SACD) |
ベートーヴェン:交響曲第7番、 ピアノ,ヴァイオリンとチェロのための三重協奏曲 |
ゴルダン・ニコリッチ(Vn)、 ティム・ヒュー(Vc)、ラルス・フォークト(P)、 ベルナルト・ハイティンク(指)LSO 録音:2005年11月16-27日ロンドン、バービカンセンター(ライヴ) |
|
||
| LSO-0082 LSO-0582(1SACD) |
ベートーヴェン:交響曲第2番、交響曲第6番「田園」 | ベルナルド・ハイティンク(指)LSO 録音:2005年11月16-27日バービカン・センターにてのライヴ録音 |
|
||
| LSO-0083(2CD) LSO-0583(2SACD) |
エルガー:「ジェロンティアスの夢」Op.38 | デイヴィッド・レンドール(T:ジェロンティアス)、 アンネ・ゾフィー・フォン・オッター(Ms:天使)、 アラステア・マイルズ(Bs)、 サー・コリン・デイヴィス(指)LSO&Cho 録音:2005年12月11日&13日ロンドン、バービカンセンター(ライヴ) |
|
||
| LSO-0087 LSO-0587(1SACD) |
ベートーヴェン:交響曲第4番、交響曲第8番* | ベルナルド・ハイティンク(指)LSO 録音:2006年4月19-20日、2006年4月24-25日* |
|
||
| LSO-0090 LSO-0590(1SACD) |
ベートーヴェン:交響曲第5番「運命」、交響曲第1番 | ベルナルト・ハイティンク(指)LSO 録音:2006年4月24-30日ロンドン、バービカンセンター(ライヴ) |
|
||
| LSO-0092 LSO-0592(1SACD) |
ベートーヴェン:交響曲第9番「合唱つき」 | トワイラ・ロビンソン(S)、 カレン・カーギル(A)、 ジョン・マック・マスター(T)、 ジェラルド・フィンリー(Bs)、 ベルナルト・ハイティンク(指)LSO、cho 録音:2006年4月29&30日ロンドン、バービカンセンター(ライヴ) |
|
||
| LSO-0105 LSO-0605(1SACD) |
シベリウス:交響曲第2番、 交響幻想曲「ポヒョラの娘」 |
コリン・デイヴィス(指)LSO 録音:2006年10月、2005年10月ロンドン・バービカンセンター(ライヴ) |
|
||
| LSO-0109 LSO-0609(1SACD) |
エルガー:エニグマ変奏曲Op.36、 序奏とアレグロOp.47 |
サー・コリン・デイヴィス(指)LSO 録音:2007年1月6&7日、2005年12月ロンドン、バービカンセンター(ライヴ) |
|
||
| LSO-0124 |
ジェイムズ・マクミラン:世界の贖罪*、 イゾベル・ゴーディの告白 |
クリスティン・ペンドリル(コールアングレ)*、 サー・コリン・デイヴィス(指)LSO 録音:2003年9月*、2007年2月21日ロンドン、バービカンセンター(ライヴ)・ストークス |
|
||
| LSO-0127 LSO-0627(1SACD) |
モーツァルト:レクイエム(ジュスマイア版) | アンナ・ステファニー(Ms)、 アンドルー・ケネディ(T)、 ダレン・ジェフリー(Bs)、 サー・コリン・デイヴィス(指)LSO、ロンドン交響cho 録音:2007年9月30日ロンドン、バービカンセンター(ライヴ) |
|
||
| LSO-0191(4CD) |
シベリウス:交響曲全集 交響曲第1番ホ短調Op.39 録音:2006年9月23-24日(ライヴ) 交響曲第2番ニ長調Op.43 録音:2006年9月27-28日(ライヴ) 交響曲第3番ハ長調Op.52 録音:2003年9月24日-10月2日(ライヴ) 交響曲第4番イ短調Op.63 録音:2008年6月29日-7月2日(ライヴ) 交響曲第5番変ホ長調Op.82 録音:2003年12月10-11日(ライヴ) 交響曲第6番ニ短調Op.104 録音:2002年9月28-29日(ライヴ) 交響曲第7番ハ長調Op.105 録音:2003年9月24日-10月2日(ライヴ) クレルヴォ交響曲Op.7 録音:2006年9月18日&10月9日(ライヴ) |
サー・コリン・デイヴィス(指)LSO モニカ・グロープ(Ms)、ペーテル・マッティ(Br) ロンドン交響cho 収録場所:ロンドン、バービカンセンター |
|
||
| LSO-0537(1SACD) |
シベリウス:交響曲第5番 交響曲第6番* |
サー・コリン・デイヴィス(指)LSO 録音:2003年12月10&11日ロンドン・バービカンホール(ライヴ)、2002年9月28&29日ロンドン・バービカンホール(ライヴ)* |
|
||
| LSO-0570(4SACD) |
ブラームス:交響曲全曲他 交響曲第1番ハ短調 op.68 悲劇的序曲 ヴァイオリンとチェロのための二重協奏曲 交響曲第2番ニ長調 op.73 セレナード第2番イ長調 op.16 交響曲第3番ヘ長調 op.90 交響曲第4番ホ短調 op.98 |
ベルナルト・ハイティンク(指) LSO ゴルダン・ニコリッチ(Vn)、 ティム・ヒュー(Vc) 録音:2003-2004年/バービカン・センター |
|
||
| LSO-0580 |
ベートーヴェン・ツィクルス第3弾 交響曲第3番『英雄』 「レオノーレ」序曲第2番 |
ベルナルド・ハイティンク(指)LSO 録音:2005年11月(ライヴ、DSD録音) 録音場所:ロンドン、バービカン・センター |
|
||
| LSO-0593(2SACD) |
ベートーヴェン:歌劇「フィデリオ」 | クリスティーン・ブルーワー(S)、 ジョン・マック・マスター(T)、 クリスティン・ジグムントソン(Bs)、 サリー・マチューズ(S)、 ユハ・ウーシタロ(Bs)、 アンドルー・ケネディ(T)、 ダニエル・ボロウスキ(Bs)ほか、 サー・コリン・デイヴィス(指)LSO&cho 録音:2005年5月23-25日、バービカンセンター ライヴ |
|
||
| LSO-0594(1SACD) |
ベートーヴェン:ミサ曲ハ長調Op.86、 歌劇「フィデリオ」第1幕~囚人の合唱 |
サリー・マシューズ(S)、サラ・ミンガルド(A)、 ジョン・マーク・エインズリー(T)、 アラステア・マイルズ(Bs)、 サー・コリン・デイヴィス(指)LSO&ロンドン交響cho 録音:2006年2月26日、2006年5月23-25日*、ロンドン、バービカンセンター(ライヴ) |
|
||
| LSO-0598(6SACD) ★ |
ベートーヴェン:交響曲全集、 三重協奏曲 |
ラルス・フォークト(P)、ニコリッチ(Vc)、 ティム・ヒュー(Vc)、 ベルナルト・ハイティンク(指)LSO 録音:2005-6年 |
|
||
| LSO-0601(1SACD) |
シベリウス:交響曲第1番ホ短調Op.39、 交響曲第4番イ短調Op.63* |
サー・コリン・デイヴィス(指)LSO 録音:2006年9月23日-24日、2008年6月29日-7月2日*ロンドン、バービカンセンター(ライヴ) |
|
||
| LSO-0606(2SACD) |
ベルリオーズ:聖三部作「キリストの幼時」 | ヤン・ブロン(語り手、百人隊長:T)、 カレン・カーギル(マリア:Ms)、 ウィリアム・デイズリー(ヨゼフ:Br)、 マチュー・ローズ(ヘロデ:Bs-Br)、 ピーター・ローズ(家長、ポリュドールス:Bs)、 テネブレcho、コリン・デイヴィス(指)LSO 録音:2006年12月3&4日(ライヴ) |
|
||
| LSO-0607 (2SACD+DVD) |
ヘンデル:オラトリオ「メサイア」 | スーザン・グリットン(S)、 サラ・ミンガルド(Ms)、 マーク・パドモア(T)、 アラステア・マイルズ(Bs)、テネブレcho、 サー・コリン・デイヴィス(指)LSO 録音:2006年12月10-12日ロンドン、バービカンセンター(ライヴ) ※カラー16:9サラウンドステレオ/NTSC/Region0/音声:英語/字幕なし |
|
||
| LSO-0623(2SACD) |
ベルリオーズ:歌劇「ベンヴェヌート・チェッリーニ」 | グレゴリー・クンデ(チェッリーニ) ローラ・クレイコム(テレーザ) ジョン・レリア(教皇クレメンス7世) アンドルー・ケネディ(フランチェスコ) イザベル・カルス(アスカーニオ) ジャック・インブライロ(ポンペーオ) ダーレン・ジェフリー(バルドゥッチ) ピーター・コールマン=ライト(フィエラモスカ) アンドルー・フォスター=ウィリアムズ(ベルナルディーノ) アラスデア・エリオット(カバラティア) サー・コリン・デイヴィス(指)LSO&ロンドン交響cho 録音:2007年6月26&29日ロンドン、バービカンホール(ライヴ)プロデューサー:ジェイムズ・マリンソン/エンジニア:ジョナサン・ストークス&ニール・ハッチンソン |
|
||
| LSO-0628(2SACD) ★ |
ハイドン:オラトリオ「天地創造」 | サリー・マシューズ(S天使ガブリエル、イヴ)、 イアン・ボストリッジ(T天使ウリエル)、 ディートリヒ・ヘンシェル(Br天使ラファエル、 アダム、ロンドン交響cho、 サー・コリン・デイヴィス(指)LSO 録音:2007年10月7日ロンドン、バービカンセンター(ライヴ) |
|
||
| LSO-0660(2SACD) |
マーラー:交響曲第3番ニ短調 | アンナ・ラーション(A) ロンドン交響合唱団女声合唱、 ティフィン少年cho ワレリー・ゲルギエフ( 指)LSO 録音:2007年9月24日ロンドン、バービカンホール( ライヴ) |
| LSO-0661(1SACD) |
マーラー:交響曲第6番イ短調「悲劇的」 | ワレリー・ゲルギエフ(指)LSO 録音:2007年11月22日ロンドン、バービカンホール(ライヴ) |
|
||
| LSO-0662(1SACD) |
マーラー:交響曲第4番ト長調 | ラウラ・クレイコム(S) ワレリー・ゲルギエフ(指)LSO 録音:2008年1月12日ロンドン、バービカンホール(ライヴ) プロデューサー:ジェイムズ・マリンソン エンジニア:0822231166221ニール・ハッチンソン&ジョナサン・ストークス |
|
||
| LSO-0663(1SACD) |
マーラー:交響曲第1番「巨人」 | ワレリー・ゲルギエフ(指)LSO 録音:2008年1月13日ロンドン・バービカンホール(ライヴ) |
|
||
| LSO-0664(1SACD) |
マーラー:交響曲第5番嬰ハ短調 | ワレリー・ゲルギエフ(指)LSO 録音:2010年9月26日ロンドン、バービカンホール(ライヴ) |
|
||
| LSO-0665(1SACD) |
マーラー:交響曲第7番「夜の歌」 | ワレリー・ゲルギエフ(指)LSO 録音:2008年3月7日ロンドン、バービカン・ホール(ライヴ) |
|
||
| LSO-0666(2SACD) |
マーラー:交響曲第2番ハ短調「復活」、 交響曲第10番~アダージョ* |
エレーナ・モシュク(S)、 ズラータ・ブルィチェワ(Ms)、ロンドン交響cho、 ワレリー・ゲルギエフ(指)LSO 録音:2008年4月20-21日、2008年6月5日ロンドン、バービカンホール(ライヴ)* |
|
||
| LSO-0668(1SACD) |
マーラー:交響曲第9番 | ワレリー・ゲルギエフ( 指)LSO 録音:2011年3月2 & 3日ロンドン、バービカンホール( ライヴ) |
|
||
| LSO-0669(1SACD) |
マーラー:交響曲第8番「千人の交響曲」 | ヴィクトリヤ・ヤーストレボワ(SⅠ罪深き女)、 アイリッシュ・タイナン(SⅡ贖罪の女)、 リュドミラ・ドゥディーノワ(SⅢ栄光の聖母)、 リリ・パーシキヴィ(MsⅠサマリアの女)、 ズラータ・ブルィチェワ(MsⅡエジプトのマリア)、 セルゲイ・セミシクール(Tマリア崇拝の博士)、 アレクセイ・マルコフ(Br法悦の神父)、 エフゲニー・ニキティン(Bs瞑想の神父)、 エルサム・カレッジcho, ワシントン・コーラル・アーツ・ソサエティ, ロンドン交響cho、 ワレリー・ゲルギエフ(指)LSO 録音:2008年7月9&10日ロンドン、セント・ポール大聖堂(ライヴ) |
|
||
| LSO-0670(1SACD) |
ティペット:オラトリオ「われらが時代の子」 | インドラ・トーマス(S)、藤村実穂子(A)、 スティーヴ・ダヴィスリム(T)、 マシュー・ローズ(Bs)、 サー・コリン・デイヴィス(指)LSO&ロンドン交響cho 録音:2007年12月16&18日ロンドン、バービカンホール(ライヴ) |
|
||
| LSO-0671(2SACD) |
ジェイムズ・マクミラン:聖ヨハネ受難曲(世界初演) *英語とラテン語による歌唱 |
クリストファー・モルトマン(Brキリスト)、 ロンドン交響cho(合唱指揮;ジョセフ・カレン)、 サー・コリン・デイヴィス(指)LSO 録音:2008年4月27日ロンドン、バービカンセンター(ライヴ) |
|
||
| LSO-0675 (1Blu-ray Disc Audio+5SACD) ★ |
シベリウス:交響曲全集 (1)交響曲第1番ホ短調Op.39 (2)交響曲第2番ニ長調Op.43 (3)交響曲第3番ハ長調Op.52 (4)交響曲第4番イ短調Op.63 (5)交響曲第5番変ホ長調Op.82 (6)交響曲第6番ニ短調Op.104 (7)交響曲第7番ハ長調Op.105 (8)クレルヴォ交響曲Op.7 (9)交響幻想曲「ポホヨラの娘」 (10)交響詩「大洋の女神」 |
サー・コリン・デイヴィス(指)LSO モニカ・グロープ(Ms) ペーテル・マッティ(Br) ロンドン交響cho男声合唱 録音:(1)2006年9月23-24日(ライヴ) (2)2006年9月27-28日(ライヴ) (3)2003年9月24日-10月2日(ライヴ) (4)2008年6月29日-7月2日(ライヴ) (5)2003年12月10-11日(ライヴ) (6)2002年9月28-29日(ライヴ) (72003年9月24日-10月2日(ライヴ) (8)2006年9月18日&10月9日(ライヴ) (9)2005年10月 (10)2008年6月29日&7月2日 |
|
||
| LSO-0677(1SACD) |
ラフマニノフ:交響曲第2番(完全全曲版) | ワレリー・ゲルギエフ(指)LSO 録音:2008年9月20&21日ロンドン、バービカンホール(ライヴ) |
|
||
| LSO-0681(1SACD) |
ウォルトン:オラトリオ「ベルシャザールの饗宴」* 交響曲第1番変ロ短調 |
ピーター・コールマン=ライト(Br)* ロンドン交響cho* サー・コリン・デイヴィス(指)LSO 録音:2008年9月28&30日ロンドン、バービカンホール(ライヴ)*、2005年9月23日&12月4日ロンドン、バービカンホール(ライヴ |
|
||
| LSO-0682(2SACD) |
プロコフィエフ:バレエ「ロメオとジュリエット」(全曲) | ワレリー・ゲルギエフ(指)LSO 録音:2008年11月21&23日ロンドン、バービカンホール(ライヴ) |
|
||
| LSO-0683(2SACD) ★ |
ヴェルディ:レクィエム | クリスティーン・ブルーワー(S) カレン・カーギル(Ms) スチュアート・ネイル(T) ジョン・レリア(Bs)、ロンドン交響cho ジョセフ・カレン(合唱指揮) サー・コリン・デイヴィス(指)LSO 録音:2009年1月11&14日ロンドン、バービカンセンター(ライヴ) |
|
||
| LSO-0685(1SACD) |
バルトーク:歌劇「青ひげ公の城」 | エレーナ・ジドコーワ(Msユディット)、 サー・ウィラード・ホワイト(Bs-Br青ひげ公)、 ワレリー・ゲルギエフ(指)LSO 録音:2009年1月27&29日ロンドン、バービカンホール(ライヴ) |
|
||
| LSO-0688(1SACD) |
ラフマニノフ:交響的舞曲Op.45 ストラヴィンスキー:3楽章の交響曲 |
ワレリー・ゲルギエフ(指)LSO 録音:2009年5月7&8日ロンドン、バービカンホール(ライヴ) |
|
||
| LSO-0689(1SACD) |
R・シュトラウス:アルプス交響曲 | ベルナルド・ハイティンク(指)LSO 録音:2008年6月8&10日ロンドン、バービカンセンター(ライヴ) |
|
||
| LSO-0692(1SACD) |
ドビュッシー:「海」~3つの交響的スケッチ バレエ「遊戯」* 牧神の午後への前奏曲# |
ワレリー・ゲルギエフ(指)LSO 録音:2009年9月20&24日バービカンホール(ライヴ)、2009年12月13&18日バービカンホール(ライヴ)*、2010年5月12&19日バービカンホール(ライヴ)# |
|
||
| LSO-0693(1SACD) |
ラヴェル:バレエ「ダフニスとクロエ」(全曲)* ボレロ* 亡き王女のためのパヴァーヌ# |
ワレリー・ゲルギエフ(指)LSO ロンドン交響cho 録音:2009年9月20&24日ロンドン・バービカンホール(ライヴ)、2009年12月13&18日ロンドン・バービカンホール*、2009年12月13&18日ロンドン・バービカンホール(ライヴ)# |
|
||
| LSO-0694(1SACD) |
ニールセン:交響曲第4番「不滅」 交響曲第5番* |
サー・コリン・デイヴィス(指)LSO 録音:2010年5月6&9日バービカンホール(ライヴ)、2009年10月1&4日ロンドン、バービカンホール(ライヴ)* |
|
||
| LSO-0696 (1SACD+DVD) |
ゲルギエフ~初のラヴェル・アルバム バレエ「ダフニスとクロエ」(全曲) ボレロ* 亡き王女のためのパヴァーヌ# ■ボーナスDVD[PAL] ラヴェル:ボレロ(全曲) |
ワレリー・ゲルギエフ(指)LSO ロンドン・シンフォニーCho 録音:2009年9月20 & 24日ロンドン、バービカンホール(ライヴ) 2009年12月13 & 18日ロンドン、バービカンホール(ライヴ)* 2009年12月13 & 18日ロンドン、バービカンホール(ライヴ)# ■ボーナスDVD[PAL] 収録:2009年12月18日/ロンドン、バービカンホール(ライヴ) |
|
||
| LSO-0700(2SACD) |
ヴェルディ:歌劇「オテロ」 | サイモン・オニール(Tオテロ) ジェラルド・フィンリー(Bs-Brイヤーゴ) アラン・クレイトン(Tカッシオ) ベン・ジョンソン(Tロデリーゴ) アレクサンドル・ツィンバリュク(Bsロドヴィーコ) マシュー・ローズ(Bsモンターノ) ルーカス・ヤコブスキ(Bs伝令) アンネ・シュヴァネヴィルムス(Sデズデモナ) エウフェミア・トゥファーノ(Sエミーリア) ロンドン交響cho コリン・デイヴィス(指)LSO *イタリア語歌唱 録音:2009年12月3&6日ロンドン、バービカンセンター(ライヴ) |
|
||
| LSO-0701(2SACD) |
R・シュトラウス:歌劇「エレクトラ」[ドイツ語歌唱] | エレクトラ:ジャンヌ=ミシェル・シャルボネ(S) クリソテミス:アンゲラ・デノケ(S) クリテムネストラ:フェリシティ・パーマー(Ms) エギスト:イアン・ストレイ(T) オレスト:マティアス・ゲルネ(Br) 監視の女 / クリテムネストラの腹心の女:エカテリーナ・ポポワ(S) 第1の下女:オリガ・レフコワ(Ms) 第2の下女 / クリテムネストラの裾持ちの女:エカテリーナ・セルゲーエワ(Ms) 第3の下女:ワルワラ・ソロヴィエワ(A) 第4の下女:タチヤナ・クラフツォワ(S) 第5の下女:リヤ・シェフツォワ(A) 若い下僕:アンドレイ・ポポフ(T) 年老いた下僕 / オレストの扶養者:ヴヤニ・ムリンデ(Bs-Br) ワレリー・ゲルギエフ(指)LSO&Cho 録音:2010年1月12 & 14日ロンドン、バービカンホール(ライヴ) |
|
||
 LSO-0702(2SACD) |
ハイドン:交響曲集/コリン・デイヴィス (1)交響曲第92番ト長調Hob.I:92「オックスフォード」 (2)交響曲第93番ニ長調Hob.I:93 (3)交響曲第97番ハ長調Hob.I:97 (4)交響曲第98番変ロ長調Hob.I:98 (5)交響曲第99番変ホ長調Hob.I:99 |
コリン・デイヴィス(指)LSO 録音:(1)2011年10月2 & 4日バービカンホール(ライヴ) (2)2011年12月11 & 13日バービカンホール(ライヴ) (3)2010年5月6 & 9日バービカンホール(ライヴ) (4)2011年12月4 & 6日バービカンホール(ライヴ) (5)2011年5月26日& 6月2日バービカンホール(ライヴ) |
|
||
| LSO-0708(2SACD) |
ハイドン:オラトリオ「四季」(ドイツ語歌唱) | ミア・パーション(Sハンネ) ジェレミー・オヴェンデン(Tルーカス) アンドルー・フォスター=ウィリアムズ(Brシモン) ロンドン交響cho キャサリン・エドワーズ(Cem) サー・コリン・デイヴィス(指)LSO 録音:2010年6月26-27日ロンドン、バービカンセンター(ライヴ) プロデューサー:ジェイムズ・マリンソン エンジニア:ジョナサン・ストークス |
|
||
 LSO-0710(2SACD) |
チャイコフスキー:交響曲集 交響曲第1番ト短調Op.13「冬の日の幻想」 交響曲第2番ハ短調Op.17「小ロシア」* 交響曲第3番ニ長調Op.29「ポーランド」# |
ワレリー・ゲルギエフ(指)LSO 録音:2011年1月18 & 23日ロンドン、バービカンホール(ライヴ) 2011年3月23 & 24日ロンドン、バービカンホール(ライヴ)* 2011年5月20日チューリヒ、トーンハレ(ライヴ)# |
|
||
| LSO-0715(1SACD) |
ニールセン:交響曲第1番ト短調Op.7 交響曲第6番「素朴な交響曲」* |
コリン・デイヴィス( 指)LSO 録音:2011年10月2&4日ロンドン、バービカンホール( ライヴ) 2011年5月26日& 6月2日ロンドン、バービカンホール( ライヴ)* |
|
||
| LSO-0716(1SACD) |
ブルックナー:交響曲第4番「ロマンティック」(ハース版) | ベルナルド・ハイティンク(指)LSO 録音:2011年6月14&16日ロンドン、バービカンセンター(ライヴ) プロデューサー:ジェイムズ・マリンソン バランス・エンジニア:ジョナサン・ストークス 音声編集:ジョナサン・ストークス&ニール・ハッチンソン |
|
||
| LSO-0719(2SACD) |
ブリテン:戦争レクィエム | サビーナ・ツビラク(S) イアン・ボストリッジ(T) サイモン・キーンリーサイド(Br) エルサム・カレッジ少年cho ロンドン交響cho ジャナンドレア・ノセダ(指)LSO、 録音:2011年10月9&11日ロンドン、バービカンホール(ライヴ) |
|
||
 LSO-0720(1SACD) |
ティオムキンの映画音楽の世界 ディミトリ・ティオムキン:「シラノ・ド・ベルジュラック」(1951)-序曲 組曲「アラモ」(1960) 「老人と海」(1958)-メイン・テーマ、クバーナ&フィナーレ 「4枚のポスター」(1952)-序曲 組曲「ジャイアンツ」(1956) 「ローマ帝国の滅亡」(1964)-愛の翳り[インストゥルメンタル・テーマ] 「真昼の決闘」(1952)より主題歌「Do Not Forsake Me, Oh My Darlin'」* 「ローハイド」(1959)-テーマ * 組曲「紅の翼」(1954) ヒッチコック組曲:「ダイヤルMを廻せ!」(1954)&「見知らぬ乗客」(1951) 「野性の息吹」(1958)-主題歌 # 「サンダウナーズ」(1960)-テーマ 「サーカスの世界」(1964)-ジョン・“デューク”・ウェインのマーチ ・「ピラミッド」(1955)-主題歌&ファラオの行進 # 「友情ある説得」(1956)-フェア 「友情ある説得」-主題歌「Thee I Love」 *# |
ホイットニー・クレア・カウフマン(Vo)# アンドルー・プレイフット(Vo)* ロンドン・ヴォイセズ リチャード・カウフマン(指)LSO 録音:2011年10月27日ロンドン、バービカンホール(ライヴ) プロデューサー:ジェイムズ・マリンソン / エンジニア:ジョナサン・ストークス&ニール・ハッチンソン |
|
||
| LSO-0722(1SACD) |
ニールセン:交響曲第2番「四つの気質」 交響曲第3番「ひろがりの交響曲(シンフォニア・エスパンシヴォ)」* |
ルーシー・ホール(S)* マーカス・ファーンズワース(Br)* サー・コリン・デイヴィス(指)LSO 録音:2011年12月4 & 6日ロンドン、バービカンホール(ライヴ) 2011年12月11 & 13日ロンドン、バービカンホール(ライヴ)* |
|
||
| LSO-0726(2SACD) |
ウェーバー:歌劇「魔弾の射手」 | サイモン・オニール(テノール:マックス) ラルス・ヴォルト(バス‐バリトン:カスパール) クリスティーン・ブルーワー(ソプラノ:アガーテ) サリー・マシューズ(ソプラノ:エンヒェン) シュテファン・ローゲス(バス‐バリトン:オットカール/ザミエル) マーティン・スネル(バス:クーノー) マーカス・ファーンズワース(バリトン:キリアン) ギドン・サクス(バス:隠 者) ルーシー・ホール(ソプラノ:花嫁に付き添う4人の乙女) マルコム・シンクレア(語り) ロンドン・シンフォニー・コーラス サー・コリン・デイヴィス(指)LSO 録音:2012年4月19日 & 21日/ロンドン、バービカン・ホール(演奏会形式によるライヴ上演) |
|
||
| LSO-0728(1SACD) |
バッハ:無伴奏ヴァイオリン・パルティータ第2番ニ短調BWV
1004、ルターのコラール集 ああ 主よ、あなたの愛しい天使に命じて(ヨハネ受難曲BWV 245) パルティータ第2番:アルマンド パルティータ第2番:クラント キリストは死の縄目につながれたり(BWV 4) パルティータ第2番:サラバンド 死に打ち勝てる者は絶えてなかりき(BWV 4) パルティータ第2番:ジグ いつの日かわれ去り逝くとき(マタイ受難曲BWV 244) シャコンヌ[ヘルガ・テーネのレアリゼーションによる、ヴァイオリンと4声のコーラスのための] フォーレ:レクィエム |
ゴルダン・ニコリッチ((Vn) グレース・デイヴィッドソン(S) ウィリアム・ゴーント(Br) テネブレCho ナイジェル・ショート(指) ロンドン交響楽団室内アンサンブル 録音:2012年 5月ロンドン、セント・ジャイルズ・クリップルゲイト教会(ライヴ ) |
|
||
 LSO-0729(2SACD) |
ベルリオーズ:レクィエム Op.5 | バリー・バンクス(T) ロンドン・シンフォニー・コーラス、 ロンドン・フィルハーモニーCho コリン・デイヴィス(指)LSO 録音:2012年6月25 & 26日ロンドン、セント・ポール大聖堂(ライヴ) |
|
||
| LSO-0730 (10SACD) ★ |
マーラー:交響曲全集 (1)交響曲第1番ニ長調「巨人」 (3)交響曲第2番ハ短調「復活」 (4)交響曲第3番ニ短調~第1楽章 (5)交響曲第3番ニ短調~第2-第6楽章 (6)交響曲第4番ト長調 (7)交響曲第5番嬰ハ短調 (8)交響曲第6番イ短調「悲劇的」 (9)交響曲第7番ホ短調「夜の歌」 (10)交響曲第8番「千人の交響曲」 (11)交響曲第9番ニ長調 |
ワレリー・ゲルギエフ(指)LSO (1)録音:2008年1月13日バービカンホール(ライヴ) DSD 5.0 (2)録音:2008年6月5日バービカンホール(ライヴ) DSD 5.0 (3)エレーナ・モシュク(ソプラノ) ズラータ・ブルィチェワ(メゾ・ソプラノ) ロンドン交響Cho 録音:2008年4月20、21日バービカンホール(ライヴ) DSD 5.0 (4)(5)アンナ・ラーション(Ms)、ティフィン少年Cho、ロンドン交響Cho 録音:2007年9月24日バービカンホール(ライヴ) DSD 5.0 (6)ラウラ・クレイコム(S) 録音:2008年1月12日バービカンホール(ライヴ) DSD 5.0 (7)録音:2010年9月26日バービカンホール(ライヴ) DSD 5.1 (8)録音:2007年11月22日バービカンホール(ライヴ) DSD 5.0 (9)録音:2008年3月7日バービカンホール(ライヴ) DSD 5.0 (10)ヴィクトリヤ・ヤーストレボワ(S Ⅰ 罪深き女)、アイリッシュ・タイナン(S Ⅱ 贖罪の女)、リュドミラ・ドゥディーノワ(S Ⅲ 栄光の聖母)、リリ・パーシキヴィ(Ms Ⅰ サマリアの女)、ズラータ・ブルィチェワ(Ms Ⅱ エジプトのマリア)、セルゲイ・セミシクール(T マリア崇拝の博士)、アレクセイ・マルコフ(Br 法悦の神父)、エフゲニー・ニキティン(Bs 瞑想の神父)、エルサム・カレッジCho 、ワシントン・コーラル・アーツ・ソサエティ、ロンドン交響Cho、録音:2008年7月9 & 10日セント・ポール大聖堂(ライヴ) 5.1 (11)録音:2011年3月2 & 3日バービカンホール(ライヴ) DSD 5.1 |
|
||
| LSO-0731(1SACD) |
シマノフスキ:交響曲第1番ヘ短調 Op.15 交響曲第2番変ロ長調 Op.19 |
ワレリー・ゲルギエフ (指)LSO 録音:2012年9、10月 バービカン・ホール(ライヴ) |
|
||
| LSO-0733(2SACD) |
ブラームス:交響曲第1番ハ短調Op.68 交響曲第2番Op.73 悲劇的序曲Op.81 ハイドンの主題による変奏曲 |
ワレリー・ゲルギエフ (指)LSO 録音:2012年9月、10月、12月 バービカン・ホール(ライヴ) |
|
||
| LSO-0737(1SACD) |
ブラームス:交響曲第3番ヘ長調op. 90 交響曲第4番ホ短調op. 98* |
ワレリー・ゲルギエフ(指)LSO 録音:2012年12月11日&18日 2012年12月12日&19日* 共にバービカンホール(ライヴ) |
|
||
| LSO-0739(1SACD) |
シマノフスキ:交響曲第3番Op.27「夜の歌」 協奏交響曲(交響曲第4番Op.60) スターバト・マーテルOp.53(ポーランド語歌唱) |
トビー・スペンス(T)、 デニス・マツーエフ(P)、 サリー・マシューズ(S)、 エカテリーナ・グバノワ(Ms)、 コスタス・スモリギナス(Br)、 ワレリー・ゲルギエフ (指) LSO&Cho サイモン・ハルジー(合唱指揮) 録音:2012年12月、2013年3月 バービカン・ホール(ライヴ) |
|
||
| LSO-0744(1SACD) |
ターネイジ:残骸から スペランツァ |
ホーカン・ハーデンベルガー(Tp) ダニエル・ハーディング(指)LSO 録音:2013年2月5、7日/バービカン・ホール(ライヴ) |
|
||
| LSO-0745(1SACD) |
ベートーヴェン:ピアノ協奏曲第2番変ロ長調 op.19 三重協奏曲 ハ長調 op.56* |
ベルナルト・ハイティンク(指)LSO マリア・ジョアン・ピリス(P) ラルス・フォークト(P)*、 ゴルダン・ニコリッチ(Vn)* ティム・ヒュー(Vc)* 録音:2013年2月、2005年* |
|
||
| LSO-0746(1SACD) |
ブルックナー:交響曲第9番(ノーヴァク版) | ベルナルド・ハイティンク(指)LSO 録音:2013年2月17 & 21日/ロンドン、バービカンセンター(ライヴ) プロデューサー:ジェイムズ・マリンソン バランス・エンジニア:アンドルー・ハリファクス&ジョナサン・ストークス 編集、ミキシング&マスタリング:ニール・ハッチンソン&ジョナサン・ストークス |
|
||
| LSO-0748(1SACD) |
ブラームス:ドイツ・レクィエム | サリー・マシューズ(S) クリストファー・マルトマン(Br) ロンドン交響Cho サイモン・ハルジー(合唱 指揮) ワレリー・ゲルギエフ(指)LSO 録音:2013年3月30&31日/ロンドン、バービカンホール(ライヴ) |
|
||
| LSO-0749(2SACD) |
ブリテン:歌劇「ねじの回転」 | アンドルー・ケネディ(T 前口上,ピーター・クイント) サリー・マシューズ(S 家庭教師) マイケル・クレイトン=ジョリ(Bs マイルズ) ルーシー・ホール(S フローラ) キャサリン・ウィン=ロジャース(Ms グロース夫人) キャサリン・ブロデリック(S ジェスル嬢) リチャード・ファーンズ(指)LSO 録音:2013年4月16、18日、ロンドン(ライヴ録音) |
|
||
| LSO-0751(1SACD) |
ストラヴィンスキー:バレエ「ミューズを司るアポロ」 オペラ=オラトリオ「エディプス王」 |
ジェニファー・ジョンストン(S:イオカステ) チュアート・スケルトン(T:エディプス王) ギドン・サクス(Bs:クレオン) ファニー・アルダン(語り) モンテヴェルディ合唱団男声Cho ジョン・エリオット・ガーディナー(指)LSO 録音:2013年4月25日& 5月1日/ロンドン、バービカン・ホール(ライヴ) プロデューサー:ニコラス・パーカー |
|
||
| LSO-0752(1SACD) |
チャイコフスキー:弦楽セレナード.ハ長調op. 48 バルトーク:ディヴェルティメントSz. 113 |
ロマン・シモヴィチ(リーダー) LSO弦楽アンサンブル 録音:2013年10月27日/ロンドン、バービカン・ホール(ライヴ) |
|
||
| LSO-0757 (1SACD+Bluray-Audio) |
ベルリオーズ:序曲「ウェイヴァリー」Op. 1 幻想交響曲 Op. 14 ■特典映像 ベルリオーズ:幻想交響曲 Op. 14(全曲演奏) |
ワレリー・ゲルギエフ(指)LSO 録音:2013年10月31日 & 11月14日/ロンドン、バービカンホール(ライヴ) [SACD : DSD5.1 surround stereo / 2.0 stereo] [Pure Audio Blu ray : 5.1 DTS-HD Master Audio (24bit/192kHz), 2.0 LPCM (24bit/192kHz)] ■特典映像 ワレリー・ゲルギエフ(指)LSO 収録:2013年11月14日/ロンドン、バービカンホール(ライヴ) |
|
||
| LSO-0760(1SACD) |
ベルリオーズ:交響曲「イタリアのハロルド」 カンタータ「クレオパトラの死」H. 36~「抒情的情景」「瞑想曲」 |
アントワーヌ・タムスティ(Va) カレン・カーギル(Ms) ワレリー・ゲルギエフ(指)LSO 録音:2013年11月1 & 12日/ロンドン、バービカンホール(ライヴ) プロデューサー:ジェイムズ・マリンソン エンジニアリング、ミキシング&マスタリング:Classic Sound Ltd |
|
||
| LSO-0762(2SACD) |
ベルリオーズ:劇的交響曲「ロメオとジュリエット」 | ワレリー・ゲルギエフ(指)LSO ギルドホール・スクール・シンガーズ オリガ・ボロディナ(Ms) ケネス・ターヴァー(T) エフゲニー・ニキーチン(Bs-Br) 録音:2013年11月6、13日バービカン・ホール(ライヴ) |
|
||
| LSO-0765 (1SACD+1Bluray audio) |
メンデルスゾーン:序曲「フィンガルの洞窟」 シューマン:ピアノ協奏曲 メンデルスゾーン:交響曲第3番「スコットランド」 ■特典映像 メンデルスゾーン:序曲「フィンガルの洞窟」 シューマン:ピアノ協奏曲イ短調Op. 54 メンデルスゾーン:交響曲第3番「スコットランド」 |
マリア・ジョアン・ピリス(P) ジョン・エリオット・ガーディナー(指)しLSO 録音:2014年1月21日/ロンドン、バービカン・ホール(ライヴ) ■特典映像 マリア・ジョアン・ピリス(P) ジョン・エリオット・ガーディナー(指)LSO 収録:2014年1月21日/ロンドン、バービカン・ホール(ライヴ) |
|
||
 LSO-0766 (8SACD+4CD +1DVD) ★ |
コリン・デイヴィス/LSOライヴ録音選集 (1)ベルリオーズ:幻想交響曲 (2)ドヴォルザーク:交響曲第9番「新世界より」 (3)ベルリオーズ:序曲「宗教裁判官」o (4)ベルリオーズ:テ・デウム (5)シベリウス:交響詩「大洋の女神」 (6)ヴォーン・ウィリアムズ:交響曲第4番 (7)ベルリオーズ:歌劇「トロイアの人々」 (8)エルガー:エニグマ変奏曲op.36 (9)エルガー:序奏とアレグロop.47 (10)シベリウス:交響曲第2番ニ長調 (11)シベリウス:交響幻想曲「ポホヨラの娘」 (12)ティペット:オラトリオ「われらが時代の子」 (13)ウォルトン:オラトリオ「ベルシャザールの饗宴」 (14)ウォルトン:交響曲第1番変ロ短調 ■特典DVD ドキュメンタリー「The Man Behind the Music」 |
全て、コリン・デイヴィス(指)LSO (1)※初SACD化 録音:2000年9月29-30日ロンドン、バービカンホール(ライヴ) (2)※初SACD化 録音:1999年9月ロンドン、バービカンホール(ライヴ) (3)※初出 録音:2006年9月27&28日ロンドン、バービカンホール(ライヴ) (4)※初出 コリン・リー(T)、ロンドン交響Cho、エルサム・カレッジCho 録音:2009年2月22&23日ロンドン、バービカンホール(ライヴ) (5)※初出 録音:2008年6月29日&7月2日ロンドン、バービカンホール(ライヴ) (6)※初出 録音:2008年9月24日ロンドン、バービカンホール(ライヴ) (7)ベン・ヘップナー(T)、ミシェル・デ・ヤング(Ms)、ペトラ・ラング(Ms)、サラ・ミンガルド(A)、ペーテル・マッテイ(Br)、スティーヴン・ミリング(Bs)、ケネス・ターヴァー(T)、トビー・スペンス(T)、ロンドン交響Cho 録音:2000年12月3、6、7日&9日ロンドン、バービカンホール(ライヴ) (8)録音:2007年1月6&7日ロンドン、バービカンホール(ライヴ) (9)録音:2005年9月23日&12月9日ロンドン、バービカンホール(ライヴ) (10)録音:2006年9月27&28日ロンドン、バービカンホール(ライヴ) (11)録音:2005年9月18日&10月9日ロンドン、バービカンホール(ライヴ) (12)インドラ・トーマス(S)、藤村実穂子(A)、スティーヴ・ダヴィスリム(T)、マシュー・ローズ(Bs)、ロンドン交響Cho 録音:2007年12月16&18日ロンドン、バービカンホール(ライヴ) (13)ピーター・コールマン=ライト(Br)、ロンドン交響Cho 録音:2008年9月28&30日ロンドン、バービカンホール(ライヴ) (14)録音:2005年9月23日&12月4日ロンドン、バービカンホール(ライヴ) ■特典DVD ※初出 監督:ライナー・モリッツ 字幕:日仏独伊西 ※ベルリオーズの「トロイアの人々」のみ通常盤CD。他全てSACDハイブリッド盤。 |
|
||
| LSO-0767(1SACD) ★ |
ピーター・マクスウェル・デイヴィス:交響曲第10番op. 327「アラ・リチェルカ・ディ・ボッロミーニ」(2013-14)* アンジェイ・パヌフニク:交響曲第10番(1988) |
マルクス・ブッター(Br)* ロンドン交響Cho* アントニオ・パッパーノ(指)LSO 録音:2014年2月2日ロンドン・バービカン・ホール(世界初演ライヴ)* 2014年10月19日ロンドン・バービカン・ホール(ライヴ) |
|
||
| LSO-0769(1SACD) KKC-5653 (1SACD+1 Bluray Disc Audio) 日本語帯・解説付 税込定価 |
メンデルスゾーン:交響曲第1番 ハ短調 op.11(1824) 交響曲第4番「イタリア」[1833年版] |
ジョン・エリオット・ガーディナー(指) LSO 録音:2014年3月23日、2016年2月16日ロンドン・バービカン・ホール(ライヴ) |
|
||
| LSO-0770(2SACD) |
スクリャービン:交響曲第1番ホ長調Op.26 第2番ハ短調「悪魔的な詩」Op.29/ |
ワレリー・ゲルギエフ (指)LSO エカテリーナ・セルゲイエワ(Ms) アレクサンドル・ティムチェンコ(Br) 録音:2014年3月30日、4月10日*バービカン・ホール(ライヴ) |
|
||
| LSO-0771(1SACD) |
スクリャービン:交響曲第3番ハ短調op. 43「神聖な詩」 交響曲第4番op. 54「法悦の詩」 |
ワレリー・ゲルギエフ(指)LSO 録音:2014年3月30日(第4番)、2014年4月13日(第3番)/ロンドン、バービカンホール(ライヴ) |
|
||
| LSO-0775 (1SACD+Bluray audio) |
ジョン・エリオット・ガーディナー~メンデルスゾーン・シリーズVol.2 交響曲第5番「宗教改革」 序曲「静かな海と楽しい航海」 序曲「ルイ・ブラス」* |
ジョン・エリオット・ガーディナー(指)LSO 録音:2014年3月23日*、2014年10月2日/ロンドン、バービカン・ホール(ライヴ) |
|
||
| LSO-0779(1SACD) |
ラフマニノフ:交響曲第3番 バラキレフ:交響詩「ロシア」 |
ワレリー・ゲルギエフ(指)LSO 録音:2014年11月11 & 13日/ロンドン、バービカンホール(ライヴ) |
|
||
| LSO-0781(1SACD) |
ラフマニノフ:晩祷Op.37 | サイモン・ホールジー(指) ロンドン交響楽団Cho 録音:2014年11月26日/バービカン・ホール(ライヴ) |
|
||
 LSO-0782 (2SACD hybrid + 1Pure Audio Blu-ray) ★ |
シューマン:オラトリオ「楽園とペリ」op. 50 | サリー・マシューズ(S:ペリ) マーク・パドモア(T:語り) ケイト・ロイヤル(S) ベルナルダ・フィンク(A) アンドルー・ステイプルズ(T) フローリアン・ベッシュ(Bs-Br) ロンドン・シンフォニー・コーラス、 サイモン・ハルシー(合唱指揮) サー・サイモン・ラトル(指)LSO 収録:2015年1月11日ロンドン、バービカン・ホール(ライヴ) |
|
||
| LSO-0784(1SACD) |
ラフマニノフ:交響曲第1番ニ短調Op.13 バラキレフ:交響詩「タマーラ」 |
ワレリー・ゲルギエフ(指)LSO 録音:2015年2月19日 バービカン・ホール(ライヴ) |
|
||
| LSO-0786(1SACD) |
シューベルト:弦楽四重奏曲第14番ニ短調 D810「死と乙女」(マーラー編曲による弦楽オーケストラ版) ショスタコーヴィチ:室内交響曲ハ短調 op.110a(バルシャイによる弦楽四重奏曲第8番の編曲) |
LSO弦楽アンサンブル ロマン・シモヴィチ(リーダー) 録音:2015年4月26日/ロンドン、バービカン・ホール(ライヴ) |
|
||
 LSO-0789 (1SACD+Bluray-Audio) ★ |
ニールセン:交響曲全集(全6曲) | ルーシー・ホール(S) マーカス・ファーンズワース(Br) サー・コリン・デイヴィス(指)LSO 録音:2011年10月2 & 4日(第1番)、2011年12月4 & 6日(第2番)、2011年12月11 & 13日(第3番)、2010年5月6 & 9日(第4番)、2009年10月1 & 4日(第5番)、2011年5月26 日& 6月2日(第6番)/ロンドン、バービカンホール(ライヴ) |
|
||
 LSO-0790 (3SACD+Bluray Disc Audio) |
ドビュッシー:歌劇「ペレアスとメリザンド」 | サイモン・ラトル(指)LSO ロンドンSOchocho メリザンド:マグダレーナ・コジェナー(S) ペレアス:クリスティアン・ゲルハーヘル(Bs) ゴロー:ジェラルド・フィンリー(Bs-Br) ジュヌヴィエーブ:ベルナルダ・フィンク(Ms)他 録音:2016年1月9-10日、バービカン・ホール(ライヴ)、DSD128fs |
|
||
| LSO-0792(1SACD) |
エルガー:序奏とアレグロ ヴォーン・ウィリアムズ:ファンタジア ブリテン:フランク・ブリッジの主題による変奏曲 |
LSO弦楽アンサンブル ロマン・シモヴィチ(リーダー ) 録音:2015年2月3日、バービカン・ホール(DSD128fs) |
|
||
 LSO-0795 (1SACD+Blu-ray Disc Audio) ボーナス映像付き |
メンデルスゾーン:「真夏の夜の夢」序曲op.21 劇中音楽「真夏の夜の夢」op.61〔プロローグ/No.1 スケルツォ(スケルツォ)/No.2 リステッソ・テンポ/No.2a アレグロ・ヴィヴァーチェ(情景と妖精の行進曲)/No.3 合唱付きのうた(二人のソプラノのための歌と女声合唱曲/No.4 アンダンテ(情景)/No.5 アレグロ・アッパッショナート(間奏曲)/No.7 夜想曲(コン・モート・トランクイッロ)/No.8 アンダンテ(夜想曲)/No.9 結婚行進曲&No.12 アレグロ・ヴィヴァーチェ・コメ・プリモ(情景)/フィナーレ〕 交響曲第1番(Blurayに収録) |
ジョン・エリオット・ガーディナー(指) LSO モンテヴェルディcho ナレーション:チェリ・リン・チッソーネ、アレクサンダー・ノックス、フランキー・ウェイクフィールド 録音:2016年2月16日、バービカン・ホール、ライヴ録音(DSD 128fs) |
|
||
| LSO-0798 (1SACD+1Blu-ray Disc Audio) |
トマス・アデス(b.1971):作品集 Asyla アサイラ op.17 (1997) Tevot テヴォット(2005-2006) Polaris ポラリス(オーケストラのための) op.29(2010) ブラームス(2001) |
トマス・アデス(指)LSO サミュエル・デラ・ジョンソン(Br) 録音:2016年3月バービカン・センター(ライヴ) |
|
||
| LSO-0800(1SACD) |
ヴェルディ:レクイエム | エリカ・グリマルディ(S) ダニエラ・バルチェッローナ(A) フランチェスコ・メーリ(T) ミケレ・ペルトゥージ(バス) ジャナンドレア・ノセダ(指)LSO ロンドン交響楽団cho 録音:2016年9月18,20日バービカン・センター(ライヴ) |
|
||
| LSO-0802(2SACD) |
ショスタコーヴィチ: 交響曲第5番ニ短調 交響曲第1番ヘ短調* |
ジャナンドレア・ノセダ(指)LSO 録音:2016年9月22日]、2019年3月27-28日* バービカン・センター |
|
||
| LSO-0803 (1SACD+1 Blu-ray Disc Audio) |
メンデルスゾーン:交響曲第2番「賛歌」op.52(1840) | ルーシー・クロウ(S) ユルギタ・アダ モ ニテ(Ms) マイケル・スパイアーズ(T) サー・ジョン・エリオット・ガーディナー(指)LSO モンテヴェルディcho 録音:2016年10月16&20日、バービカン・センター(ライヴ)DSD 128fs |
|
||
| LSO-0804(1SACD) |
モーツァルト:ヴァイオリン協奏曲集 協奏曲第1番変ロ長調 K207〔カデンツァ/ズナイダー〕 協奏曲第2番ニ長調 K211〔カデンツァ/ズナイダー〕 協奏曲第3番ト長調 K216〔カデンツァ/ズナイダー〕 |
ニコライ・ズナイダー(指&Vn/ 'クライスラー
'( グァルネリ・デル・ジェス )) LSO 録音:2016&2017、ライヴ(バービカン・ホール) |
|
||
| LSO-0807(1SACD) |
モーツァルト:ヴァイオリン協奏曲集 ヴァイオリン協奏曲第4番 ニ長調 K.218(カデンツァ:ニコライ・ズナイダー) ヴァイオリン協奏曲第5番 イ長調 K.219「トルコ風」(カデンツァ:ニコライ・ズナイダー) |
ニコライ・ズナイダー(指&Vn(‘クライスラー’(
グァルネリ・デル・ジェス )) LSO 録音:2016年12月18日、2017年5月14日、ライヴ(バービカン・ホール) |
|
||
| LSO-0808(1SACD) |
ハイドン・想像上のオーケストラの旅 I. オラトリオ『天地創造』より第1部 第1日「ラルゴ:混沌の描写」 II. 『十字架上のキリストの最後の7つの言葉』より終曲「地震」 IIIa. 『無人島』Hob.Ia:13よりシンフォニア〈ラルゴ-ヴィヴァーチェ・アッサイ〉 IIIb. 『無人島』Hob.Ia:13よりシンフォニア〈アレグレット-ヴィヴァーチェ〉 IV. 交響曲第64番 イ長調 Hob.I:64「時の移ろい」より第2楽章〈ラルゴ〉 V. 交響曲第6番 ニ長調「朝」Hob.I:6より第3楽章〈メヌエット〉 VI. 交響曲第46番 ロ長調 Hob.I:46よりフィナーレ〈プレスト〉 VII. 交響曲第60番 ハ長調 Hob.I:60「うかつ者」よりフィナーレ〈プレスティッシモ〉 VIII. オラトリオ『四季』より第4部 冬「序奏」 IXa. 交響曲第45番 嬰ヘ短調 Hob.I:45「告別」よりフィナーレ〈プレスト〉 IXb. 交響曲第45番 嬰ヘ短調 Hob.I:45「告別」よりフィナーレ〈アダージョ〉 X. 笛時計のための三重曲集よりHob.XIX:1-32(抜粋) XI. 交響曲第90番 ハ長調 Hob.I:90よりフィナーレ〈アレグロ・アッサイ〉 (最終トラックでは、偽終始の箇所と、楽曲の最後それぞれに拍手が収録されています) |
サー・サイモン・ラトル(指)LSO 録音:2017年7月11&12日、バービカン・センター(ロンドン)、ライヴ |
|
||
 LSO-0809(2SACD) |
ベルリオーズ:ファウストの劫罰 | サー・サイモン・ラトル(指) LSO、ロンドン交響楽団cho ティッフィン少年cho ティッフィン少女cho ディッフィン児童cho カレン・カーギル(Ms/マルグリート) ブライアン・ハイメル(T/ファウスト) クリストファー・パーブスBs-Br/メフィストフェレス) ガボール・ブレッツ(Bs/ブランデル) 録音:2017年9月、バービカン・センター(ロンドン)ライヴ |
|
||
| LSO-0810(1SACD) |
チャイコフスキー:交響曲第4番 ムソルグスキー(ラヴェル編):展覧会の絵* |
ジャナンドレア・ノセダ(指)LSO 録音:2017年10月29日-11月1日、2018年6月3日* |
|
||
| LSO-0813(1SACD) |
バーンスタイン:ワンダフル・タウン 1序曲Overture 2 クリストファー・ストリート(Christopher Street) 3 オハイオ(Ohio) 4 コンカリング・ニューヨーク(Conquering New York) 5 100通りの抜け道(One Hundred Easy Ways to Lose a Man) 6 何という無駄(What a Waste) 8 ちょっと恋して(A Little Bit in Love) 9 パス・ザ・フットボール(Pass the Football) 10 カンヴァセーション・ピース(Conversation Piece) 11 もの静かな娘(A Quiet Girl) 12 コンガ! (Conga!) 13 間奏曲(Entr’acte) 14 マイ・ダーリン・アイリーン(My Darlin’ Eileen) 15 スウィング!(Swing) 16 静かなできごと(Quiet Incidental) 16a 繰り返し:オハイオ(Ohio (Reprise)) 17 イッツ・ラヴ(It’s Love) 18 バレエ・アット・ヴィレッジ・ヴォーテックス(Ballet at the Village Vortex) 19 音の狂ったラヴタイム(The Wrong-Note Rag) 20 繰り返し:イッツ・ラヴ(It’s Love (Reprise)) |
ダニエル・ドゥ・ニース(ルース役) アリーシャ・アンプレス(アイリーン役) ネイサン・ガン(ベイカー役) サイモン・ラトル(指)LSO LSO合唱団 録音:2017年12月、バービカン・ホール(ロンドン)、ライヴ |
|
||
| LSO-0816 (3SACD+BluRay Audio) 限定盤 ★ |
ゲルギエフ&LSO/ラフマニノフ・ボックス (1)ラフマニノフ:交響曲第1番 (2)ラフマニノフ:交響的舞曲 (3)ラフマニノフ:交響曲第2番(完全全曲版) (4)バラキレフ:交響詩「ロシア」 (5)ラフマニノフ:交響曲第3番 (6)バラキレフ:交響詩「タマーラ」 ■Blu-Ray Audio ラフマニノフ:交響曲第1-3番、交響的舞曲、バラキレフ:交響曲「ロシア」「タマーラ」の順に収録 |
ワレリー・ゲルギエフ(指)LSO 録音:(1)2015年2月19日 (2)2009年5月7 & 8日 (3)2008年9月20 & 21日 (4)2014年11月11 & 13日 (5)2014年11月11 & 13日 (6)2015年2月19日 全て、ロンドン、バービカンホール(ライヴ) |
|
||
| LSO-0818(1SACD) |
シューマン:序曲『ゲノフェーファ』 交響曲第4番(1841年オリジナル版)* 交響曲第2番ハ長調 op.61(1845) |
サー・ジョン・エリオット・ガーディナー(指)
LSO 録音:2018年3月12日、3月16日*、バービカン、ロンドン |
|
||
| LSO-0821(1SACD) |
ロトのラヴェル&ドビュッシー ラヴェル:スペイン狂詩曲 ドビュッシー:牧神の午後への前奏曲* 交響詩「海」# |
フランソワ=グザヴィエ・ロト(指) lLSO 録音:2019年4月25日、2018年1月25日*、3月38日# バービカン・ホール(ライヴ) |
|
||
| LSO-0822(1SACD) |
ショスタコーヴィチ:交響曲第8番ハ短調 op.65 | ジャナンドレア・ノセダ(指)lps 録音:2018年4月、バービカン・ホール |
|
||
| LSO-0826(4SACD) 限定盤 ★ |
メンデルスゾーン:交響曲全曲&序曲集 ■Disc1 (1)交響曲第1番(第3楽章は1824年版のメヌエット(とトリオ)/1829年「ロンドン版」のスケルツォを収録) (2)序曲「静かな海と楽しい航海」 (3)交響曲第5番「宗教改革」 ■Disc2 交響曲第2番「賛歌」 ■Disc3 (1)序曲「ルイ・ブラス」 (2)交響曲第3番「スコットランド」 (3)交響曲第4番「イタリア」 [1833年版] ■Disc4 (1)序曲「フィンガルの洞窟」 (2)「真夏の夜の夢」序曲 (3)「真夏の夜の夢」〔プロローグ/No.1 スケルツォ(スケルツォ)/No.2 リステッソ・テンポ/No.2a アレグロ・ヴィヴァーチェ(情景と妖精の行進曲)/No.3 合唱付きのうた(二人のソプラノのための歌と女声合唱曲/No.4 アンダンテ(情景)/No.5 アレグロ・アッパッショナート(間奏曲)/No.7 夜想曲(コン・モート・トランクイッロ)/No.8 アンダンテ(夜想曲)/No.9 結婚行進曲&No.12 アレグロ・ヴィヴァーチェ・コメ・プリモ(情景)/フィナーレ) ●ブルーレイ・オーディオ・ディスク(Pure Audio Blu-ray[24 bit 96kHz stereo and 5.1 multichannel]) メンデルスゾーン: (1)交響曲第1番(第3楽章は1824年版のメヌエット(とトリオ)/1829年「ロンドン版」のスケルツォを収録) (2)序曲「静かな海と楽しい航海」 (3)交響曲第5番「宗教改革」 (4)交響曲第2番「賛歌」 (5)交響曲第3番「スコットランド」 (6)交響曲第4番「イタリア」[1833年版] (7)序曲「フィンガルの洞窟」 (8)「真夏の夜の夢」序曲 (9)「真夏の夜の夢」op.61 |
【第2番】 ルーシー・クロウ(S) ユルギタ・アダモニテ(Ms) マイケル・スパイアーズ(T)、 モンテヴェルディcho 【真夏の夜の夢op.61】 ナレーション:チェリ・リン・チッソーネ、 アレクサンダー・ノックス、 フランキー・ウェイクフィールド ジョン・エリオット・ガーディナー(指) LSO ■Disc1 (1)録音:2014年3月23日、2016年2月16日 (2)録音:2014年10月2日 (3)録音:2014年10月2日 ■Disc2 録音:2016年10月16&20日 ■Disc3 (1)録音:2014年3月23日 (2)録音:2014年1月21日 (3)録音:2014年3月23日、2016年2月16 ■Disc4 (1)録音:2014年1月21日 (2)録音:2016年2月16日 (3)録音:2016年2月16日 ブルーレイディスク(Pure Audio Blu-ray[24 bit 96kHz stereo and 5.1 multichannel]) (1)録音:2014年3月23日、2016年2月16日 (2)録音:2014年10月2日 (3)録音:2014年10月2日 (4)録音:2014年3月23日 (5)録音:2014年1月21日 (6)録音:2014年3月23日、2016年2月16 (7)録音:2014年1月21日 (8)録音:2016年2月16日 (9)録音:2016年2月16日 |
|
||
| LSO-0827 (6SACD+10CD) 限定3000セット |
ベルリオーズ・オデュッセイ ■SACD (1)序曲「宗教裁判官」 (2)テ・デウム (3)レクィエム Op.5 (4)歌劇「ベンヴェヌート・チェッリーニ」 (5)聖三部作「キリストの幼時」H.130(Op.25) ■CD (1)歌劇「トロイの人々」 (3)幻想交響曲 (4)歌劇「ベアトリスとベネディクト」(歌唱:フランス語) (5)ロメオとジュリエット(歌唱:フランス語) (6)「イタリアのハロルド」 |
コリン・デイヴィス(指)LSO ■SACD (1)録音:2006年9月27 & 28日 (2)コリン・リー(T)、ロンドン交響cho, エルサム・カレッジcho【録音:2009年2月22 & 23日】 (3)バリー・バンクス(T)、ロンドンSOcho、ロンドン・フィルハーモニーcho【録音:2012年6月25 & 26日/ロンドン、セント・ポール大聖堂(ライヴ)】 (4)グレゴリー・クンデ(チェッリーニ) ローラ・クレイコム(テレーザ)、ジョン・レリア(教皇クレメンス7世)、アンドルー・ケネディ(フランチェスコ)、イザベル・カルス(アスカーニオ)、ジャック・インブライロ(ポンペーオ)、ダーレン・ジェフリー(バルドゥッチ)、ピーター・コールマン=ライト(フィエラモスカ)、アンドルー・フォスター=ウィリアムズ(ベルナルディーノ)、アラスデア・エリオット(カバラティア)、ロンドン交響cho【録音:2007年6月26&29日】 (5)ヤン・ブロン(語り手、百人隊長:T)、カレン・カーギル(マリア:Ms)、ウィリアム・デイズリー(ヨゼフ:Br)、マチュー・ローズ(ヘロデ:Bs-Br)、ピーター・ローズ(家長、ポリュドールス:Bs)、テネブレcho【録音:2006年12月3&4日】 [CD] (1)ヘップナー(T)、ラング(Ms)、デヤング(Ms)、ミンガルド(A)、マッテイ(Br)、ターヴァー(T)、ミリング(B) 他【録音:2000年12月】 (2)サッバティーニ(T)、シュコサ(Ms)、ペルトゥージ(B)、ウィルソン=ジョンソン(B)、ロンドンSOcho【録音:2000年10月】 (3)録音:2000年9月29-30日】 (4)シュコサ(Ms)、ターヴァー(T)、グリットン(S)、ミンガルド(A)、ナウリ(B) 他、ロンドンSOcho【録音:2000年6月】 (5)バルチェッローナ(Ms)、ターヴァー(T)、アナスタソフ(B)、ロンドンSO cho【録音:2000年1月】 (6)タベア・ツィンマーマン(Va)【録音:2002年3月】 ※収録場所は、レクィエム以外はすべてバービカン・ホール。 |
|
||
| LSO-0828(1SACD) |
ショスタコーヴィチ:交響曲第9番変ホ長調Op.70 交響曲第10番ホ短調Op.93 |
ジャナンドレア・ノセダ(指)LSO 録音:2018年6月24日(第10番)、2020年1月30日、2月9日(第9番)、バービカン・ホール、ロンドン(ライヴ) |
|
||
| LSO-0830(1SACD) |
ブリテン:作品集 (1) シンフォニア・ダ・レクイエム op.20 (2) 春の交響曲 (3) 青少年のための管弦楽入門 |
サー・サイモン・ラトル(指) LSO エリザ ベス・ワッツ(S)、アリス・クート(Ms)、アラン・クレイトン( テノール )、 ティフィン少年cho、ティフィン児童cho、ティフィン女学ch ロンドン響cho 録音:(1)2019年5月7,8日、(2)2018年9月16,18日、(3) 2021年5月18日、すべてバービカン・ホールでの録音 |
|
||
| LSO-0832(1SACD) |
ショスタコーヴィチ:交響曲第4番ハ短調 | ジャナンドレア・ノセダ(指)LSO 録音:2018年11月、バービカン・ホール、ロンドン |
|
||
| LSO-0833(1SACD) |
R・シュトラウス:交響詩「ツァラトゥストラはかく語り」 ドビュッシー:バレエ音楽「遊戯」* |
フランソワ=グザヴィエ・ロト(指)LSO 録音:2018年1月*、11月 バービカン・ホール(ロンドン) |
|
||
| LSO-0834(2SACD) |
バーンスタイン:『キャンディード』 | マリン・オールソップ(指)LSO LSO合唱団 レオナルド・カパルボ(テノール/キャンディード)、ジェーン・アーチボルト(ソプラノ/クネゴンデ)、アンネ・ゾフィー・フォン・オッター(メゾ・ソプラノ/オールドレディー)、サー・トーマス・アレン(バリトン/パングロス博士、ナレーター) 録音:2018年12月8&9日、バービカン・ホール(ロンドン) |
|
||
| LSO-0836(1SACD) |
バーンスタイン:プレリュード、フーガとリフ(1949) ストラヴィンスキー:エボニー協奏曲(1945) ゴリホフ(ゴンザロ・グラウ編):ナザレーノ(2000作曲/ 2009年編) |
サー・サイモン・ラトル(指)LSO ピアノ:カティア&マリエル・ラベック姉妹(ゴリホフ) クラリネット:クリス・リチャー ズ( ストラヴィンスキ ー ) ゴンザロ・グラウ、ラファエル・セグルニエ(ラテン・パーカッション) 録音:2018年12月12&13日、バービカン・ホール(ロンドン) |
|
||
| LSO-0842(1SACD) |
ブルックナー:交響曲第6番イ長調 WAB.106〔ベンヤミン=グンナー・コールス版(2015年)〕 | サー・サイモン・ラトル(指)LSO 録音:2019年1月、バービカン・ホール(ロンドン) |
|
||
| LSO-0844(1SACD) |
シューマン:交響曲第1番「春」変ロ長調 op.38 序曲「マンフレッド」op.115 交響曲第3番「ライン」 変ホ長調 op.97 |
サー・ジョン・エリオット・ガーディナー(指) LSO 録音:2019年2月10日(第1番、マンフレッド)、2月7日(第3番) バービカン・ホール(ロンドン) |
|
||
| LSO-0850(2SACD) |
ヤナーチェク:オペラ「利口な女狐の物語」、 ンフォニエッタ |
サイモン・ラトル(指) ロンドンSO 森番:ジェラルド・フィンリー(Br) 森番の妻:ポーリーン・マレファネ(S) 校長:ピーター・ホアー(T) 司祭:ヤン・マルティニク(Bs) ハラシュタ:ハンノ・ミュラー=ブラッハマン(Bs) パーセク:ヨナ・ハルトン(T) パーセクの妻:アンナ・ラプコフスカヤ(Ms) ペピーク:ポピー・デウィッド(子役) ペピークの友達フランティーク:インジ・ガリエット=ジャコビー(子役) 子供の頃のビストロウシュカ:サオワーズ・エクセルビー(子役) ビストロウシュカ:ルーシー・クロウ(S) ロンドンSO合唱団 録音:2019年6月27,29日(利口な女狐の物語/ピーター・セラーズ演出によるセミ・ステージ形式上演のライヴ録音) 2018年9月18-19日(シンフォニエッタ) いずれもバービカン・ホールにての録音 |
|
||
| LSO-0851(1SACD) |
ラフマニノフ:交響曲第2番ホ短調Op.27(完全版) | サー・サイモン・ラトル(指)LSO 録音:2019年9月、バービカン・ホール(ライヴ) |
|
||
| LSO-0855(2SACD) |
モーツァルト:管楽のための作品集 ホルン協奏曲 変ホ長調 K417 オーボエ協奏曲 ハ長調 K314 クラリネット協奏曲 イ長調 K622 協奏交響曲 変ホ長調 K297b セレナード第10番「グラン・パルティータ」 |
ハイメ・マルティン(指) ティモシー・ジョーンズ(Hrn)、 オリヴィエ・スタンキエヴィチ(Ob)、 アンドルー・マリナー(Cl)、 ジュリアナ・コッホ(Ob)、 クリス・リチャーズ(Cl)、 レイチェル・ゴフ(Fg)、 LSO木管アンサンブル、LSO 録音:2019年10月12-13日(K417,314,622,297b)、2015年10月31日(K361)/ジャーウッド・ホール(セント・ルークス) |
|
||
 LSO-0858(1SACD) KKC-6600(1SACD) 国内盤仕様 税込定価 |
ノセダ/ャイコフスキー:Sym#5 チャイコフスキー:交響曲第5番ホ短調Op.64 リムスキー=コルサコフ:「見えざる町キーテジと聖女フェヴローニャの物語」組曲 |
ジャナンドレア・ノセダ(指)LSO 録音:2019年11月3日、28日* ロンドン、バービカン・ホール(ライヴ) |
|
||
| LSO-0859(1SACD) |
ショスタコーヴィチ:交響曲第7番『レニングラード』 | ジャナンドレア・ノセダ(指)LSO 録音:2019年12月、バービカン・ホール |
|
||
| LSO-0862(1SACD) |
ベートーヴェン:オラトリオ『オリーブ山上のキリスト』op.85 | サー・サイモン・ラトル(指)LSO エルザ・ドライシヒ(S) パヴォル・ブレスリク(T) デーヴィッド・ソアー(Bs) ロンドン交響cho(合唱指揮:サイモン・ハルシー) 録音:2020年1月19日、2月13日、バービカンホール、ロンドン(ライヴ) DSD録音 |
|
||
| LSO-0867(1SACD) |
ヴォーン=ウィリアムズ:交響曲第4番ヘ短調 交響曲第6番ホ短調 |
アントニオ・パッパーノ(指)LSO 録音:2019年12月12日(第4番)、2020年3月15日(第6番)、バービカン・ホール、ロンドン(ライヴ) |
|
||
 LSO-0875(2SACD) KKC-6557(2SACD) 国内盤仕様 (日本語解説付) 税込定価 |
2021年グンナー=コールス版「ブル4」の世界初録音! ■CD1 ブルックナー:交響曲第4番(1878-81年/Cohrs A04B) 第1楽章:Bewegt, nicht zu schnell(動いて、しかし速すぎずに)(作業段階B, 1881) 第2楽章:Andante quasi Allegretto(作業段階B, 1881) 第3楽章:Scherzo. Bewegt - Trio. Nicht zu schnell, Keinesfells schleppend-Scherzo da capo (スケルツォ。動いて/トリオ。速すぎず、遅くなりすぎず/スケルツォ・ダ・カーポ)(作業段階B, 1881) 第4楽章:Finale. Bewegt, nicht zu schnell(フィナーレ。動いて、しかし速すぎずに)(作業段階C, 1881年, カットあり版) ■CD2 ブルックナー:交響曲第4番 (1) Discarded Scherzo. Sehr schnell ? Trio. Im gleichen Tempo ? Scherzo da capo (1874/revised 1876;Cohrs A04B-1)(取り外されたスケルツォ-非常に速く/トリオ-同様のテンポで/スケルツォ・ダ・カーポ)(1874年/1876年改訂/Cohrs A04B-1) (2) Discarded Finale (‘Volksfest’). Allegro moderato 取り外されたフィナーレ(民衆の踊り)(1878; Cohrs A04B-2) (3) Andante quasi Allegretto (Work Phase A, 1878; extended initial version/1878年、作業段階A、第2楽章の当初の長いヴァージョン) (4) Finale. Bewegt; doch nicht zu schnell (Work Phase B, 1881; unabridged)(作業段階B, 1881年, カットなし版) |
サイモン・ラトル(指)LSO 録音:2021年10月、ジャーウッド・ホール、セント・ルークス、ロンドン |
|
||
| LSO-0878(1SACD) |
ショスタコーヴィチ:交響曲第15番イ長調 op.141 交響曲第6番ロ短調 op.54 |
ジャナンドレア・ノセダ(指)LSO 録音:2019年10月31日(第6番)、2022年2月6,13日(第15番) |
|
||
| LSO-0887(1SACD) |
ブルックナー:交響曲第7番ホ長調 WAB107 (Version1881?83;
Cohrs A07) 〔ベンヤミン=グンナー・コールス校訂版(2015年)による世界初録音〕 |
サイモン・ラトル(指)LSO 録音:2022年9月18日&12月1日、バービカン・ホール |
|
||
| LSO-0888(1SACD) |
ショスタコーヴィチ:交響曲第11番『1905年』 | ジャナンドレア・ノセダ(指)LSO 録音:2022年11月24日、バービカン・ホール |
|
||
| LSO-0889(2SACD) |
ヤナーチェク:歌劇「カーチャ・カバノヴァー」 | パヴロ・フンカ(サヴィオル・ヂコイ/バス・バリトン)・・・富裕な商人 サイモン・オニール(ボリス・グリゴリェヴィチ/テノール)・・・ヂコイの甥 カタリーナ・ダレイマン(マルファ・カバノヴァー/メゾ・ソプラノ)・・・愛称カバニハ/富裕な商家の未亡人 アンドルー・ステイプルス(チホン・カバノフ/テノール)・・・マルファの息子 アマンダ・マジェスキ(カチェリーナ(カーチャ)/ソプラノ)・・・チホンの妻 ラディスラフ・エルグル(ヴァーニャ・クドリャーシ/テノール)・・・ヴァルヴァラの恋人/ヂコイの執事 マグダレーナ・コジェナー(ヴァルヴァラ/メゾ・ソプラノ)・・・カバノフ家の養女 ルカーシュ・ゼマン(クリギン/バリトン)・・・クドリャーシの友人 クレール・バーネット=ジョーンズ(グラーシャ、フェクルーシャ、使用人/メゾ・ソプラノ)・・・カバノフ家の女中 サー・サイモン・ラトル(指)LSO、ロンドン響cho 録音:2023年1月11&13日、バービカン・ホール |
|
||
| LSO-0894(3SACD) |
マイヤベーア:歌劇「予言者」 | ジョン・オズボーン(T/ジャン) エリザベス・デション(Ms/フィデス(ジャンの母)) マネ・ガロヤン(S/ベルト(ジャンの恋人)) エドウィン・クロスリー=メルセル(BsBr/オーベルタル伯爵およびアナバプティスト役(一部)) ジェームス・プラット(Bs/ザッカリー(アナバプティスト)) ほか リヨン歌劇場cho ブーシュ・ドゥ・ローヌ学生cho 地中海ユース・オーケストラ LSO サー・マーク・エルダー(指) 録音:2023年7月15日、プロヴァンス大劇場(エクス=アン・プロヴァンス音楽祭) |
|
||
| LSO-0899(1SACD) |
ラヴェル:「ダフニスとクロエ」 | アントニオ・パッパーノ(指)LSO テネブレ(合唱) 録音:2024年4月10&11日、バービカン・ホール |
|
||
| LSO-0900(1SACD) |
ヴォーン・ウィリアムズ:交響曲第5番ニ長調 交響曲第9番ホ短調 |
アントニオ・パッパーノ(指)LSO 録音:2024年4月17日(第5番)、2024年12月15日(第9番) ロンドン、バービカン・ホール |
|
||
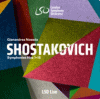 LSO-0907(10SACD) |
ショスタコーヴィチ:交響曲全集(全15曲) [Disc1] 交響曲第1番ヘ短調 op.10 交響曲第15番イ長調 op.141 [Disc2] 交響曲第2番ロ長調「十一月革命に捧げる」op.14( 交響曲第13番変ロ短調「バビ・ヤール」op.113 [Disc3] 交響曲第3番変ホ長調「メーデー」op.20 交響曲第12番ニ短調「1917年」op.112 祝典序曲 op.96 [Disc4] 交響曲第4番ハ短調 op.43 [Disc5] 交響曲第5番ニ短調 op.47 交響曲第6番ロ短調 op.54 [Disc6] 交響曲第7番ハ長調「レニングラード」op.60 [Disc7] 交響曲第8番ハ短調 op.65 [Disc8] 交響曲第9番変ホ長調 op.70 交響曲第10番ホ短調 op.93 [Disc9] 交響曲第11番ト短調「1905年」op.103 [Disc10] 交響曲第14番ト短調 op.135 |
ジャナンドレア・ノセダ(指) LSO LSOcho ロンドン・フィルハーモニーcho ヴィタリー・コワリョフ(Bs) エレナ・スティキナ(S) 録音:交響曲第1番=録音:2019年3月 交響曲第15番=録音:2022年2月 交響曲第2番=2025年4月 交響曲第13番=2023年4月 交響曲第3番=2024年6月 交響曲第12番=2025年4月 祝典序曲=2025年4月 交響曲第4番=2018年11月 交響曲第5番=2016年9月 交響曲第6番=2019年10月 交響曲第7番=2019年12月 交響曲第8番=2018年4月 交響曲第9番=2020年2月 交響曲第10番=2018年6月 交響曲第11番=2022年11月 交響曲第14番=2022年2月 |
|
||
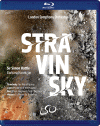 LSO-3028 (1Bluray+1DVD) |
ストラヴィンスキー:春の祭典 リゲティ:マカーブルの秘密(オペラ「グラン・マカーブル」からのコンサート用アリア集) ベルク:ヴォツェックからの3つの断章 ウェーベルン:オーケストラのための6つの小品 |
バーバラ・ハンニガン(S) サー・サイモン・ラトル(指)LSO 収録:2016年1月13日、バービカン・ホール(ライヴ/ライヴ/HD、24bit 96kHz収録) |
|
||
| LSO-3038 (1DVD+1BluRay) ★ |
ラトル~フランス・プログラム ラヴェル:クープランの墓 デュティユー:ヴァイオリン協奏曲「夢の樹」 モーリス・ドラージュ:4つのインドの詩 デュティユー:メタボール ラヴェル:バレエ「ダフニスとクロエ」第2組曲 |
サイモン・ラトル(指)LSO レオニダス・カヴァコス(Vn) ジュリア・ブ ロック(S) 収録:2016年1月13日、バービカン・ホール(ライヴ) 〔映像監督:フランソワ=ルネ・マルタン、オーディオ・プロデューサー:ニコラス・パーカー、 サウンド・エンジニアリング:クラシック・サウンド・リミテッド〕 24bit 48kHzPCM |
|
||
| LSO-3042 (1DVD+1Blu-Ray) |
メシアン:天国の色彩(天の都市の色彩) ブルックナー:交響曲第8番(1939年ハース版) |
サイモン・ラトル(指)LSO ピエール=ロラン・エマール(P) 収録:2016年4月バービカン・ホール(ロンドン)/ライヴ STEREO 24bit 48kHz PCM リージョン:all、1h44’ |
|
||
| LSO-3066 (1Bluray+1DVD) |
THIS IS RATTLE~これがラトルだ ヘレン・グライム:ファンファーレ トマス・アデス:アシュラ ハリソン・バートウィッスル:ヴァイオリン協奏曲 オリヴァー・ナッセン:交響曲第3番 エルガー:エニグマ変奏曲 op.36 |
クリスティアン・テツラフ(Vn) サー・サイモン・ラトル(指)LSO 収録:2017年9月14日(ラトルの音楽監督就任記念コンサート)、バービカンホール(ロンドン)、ライヴ 115m VIDEO FORMATS Colour. Blu-Ray: BD25 (All Regions), 16:9, HD 1080i (NTSC) DVD: DVD9 (Region 0), 16:9 (NTSC) AUDIO FORMAT 24bit 48kHz, 2.0 PCM STEREO |
|
||
| LSO-3073 (BluRay+DVD) KKC-9417 (Blu-Ray+DVD) 国内盤仕様 税込定価 |
若きドビュッシーへのオマージュ ドビュッシー:管弦楽組曲第1番(1882) ラロ:チェロ協奏曲ニ短調 ワーグナー:「タンホイザー」序曲 マスネ:歌劇「ル・シッド」~バレエ組曲 |
フランソワ=グザヴィエ・ロト(指)LSO エドガー・モロー(Vc) 録音:2018年1月21日/バービカン・ホール(ロンドン) リージョンオール PCM STEREO、24bit 48kHz 1h 30’ 12’ 【BD仕様】 1080i HD, 50BD 16:9、カラー 【DVD仕様】 NTSC 16:9、カラー |
|
||
| LSO-5061 ★ |
The Panufnik Legacies~LSOのために書き下した作品集 アンドルー・マコーマック:インセンティヴIncentive クリスティアン・メイソン:…照りつける日差しからの逃避…… from bursting suns escaping … チャーリー・パイパー:浮遊Fl?otan エロイーズ・ジン:サクラSakura エドワード・ネズビット:類似Ⅰ Parallels I エドワード・ネズビット:類似Ⅱ Parallels II ジェイソン・ヤード:ひどい幻滅!Rude Awakening! マーティン・サックリング:新生児のためのファンファーレFanfare for a Newborn Child クリストファー・メイヨー:サーマTherma エリザベス・ウィンターズ:突然の豪雨、突然の曇りSudden Squall, Sudden Shadow ヴラド・マイストロヴィチ:ハロHalo |
フランソワ=グザヴィエ・ロト(指)LSO 録音:2012年10月/ロンドン、LSOセント・ルークス プロデューサー:ジョナサン・ストークス |
|
||
| LSO-5070 |
パヌフニクの遺産Ⅱ パヌフニク変奏曲(「宇宙の祈り」の主題による10人の作曲家の共作) ダンカン・ワード:P-p-パラノイア アラステア・パット:スパイラル アーロン・パーカー:魅了された キム・B・アシュトン:波しぶき ジェームズ・モリアーティ:顆粒状の断片 エリザベス・オゴネク:鳥のように レオ・チャドバーン:茶色のレザー・ソファ ブシュラ・エル=トゥルク:切断 マシュー・カーナー:書道家の自筆 |
フランソワ=グザヴィエ・ロト(指)LSO 録音:2015年6月3、4日/聖ルカ教会(ロンドン) |
|
||
| LSO-5073 (1SACD) |
スティーヴ・ライヒ(b 1936):クラッピング・ミュージック(1972) 木片のための音楽(1973) 六重奏曲(1985) |
LSOパーカッション・アンサンブル 録音:2015年10月30日/ロンドン、LSOセント・ルークス(ライヴ)/DSD 128fs録音 レコーディング・サポート/Bowers&Wilkins |
|
||
| LSO-5074(1SACD) |
ストラヴィンスキー:兵士の物語 | LSO 室内アンサンブル 語り:マルコム・シンクレア ロマン・シモヴィチ(ヴァイオリン(LSO首席)) エディクソン・ルイス( コントラバス( ベルリン・フィル)) アンドルー・マリナー(クラリネット(LSO首席)) ラファエル・ガウフ(ファゴット(LSO 首席)) フィリップ・コブ(トランペット(LSO首席)) ダドリー・ブライト(トロンボーン(LSO首席)) ニール・パーシー(打楽器(LSO首席)) 録音:2015 年10月31日、セント・ルークス(ロンドン) |
|
||
| LSO-5075(1SACD) |
モーツァルト:セレナード第10番「グラン・パルティータ」変ロ長調 KV 361 | LSOウィンドアンサンブル オーボエ:オリヴィエ・スタンキエヴィチ*、ロジー・ジェンキンス クラリネット:アンドリュー・マリナー*、チ=ユ・モー バセットホルン:ロレンツォ・イオスコ*、クリス・リチャーズ ファゴット:ダニエル・ジェミソン*、ジュースト・ボスジク ホルン:ティム・ジョーンズ*、アンジェラ・バーンズ、アレックス・エドムントソン、ジョナサン・リプトン コントラバス:コリン・パリス (*はLSO首席奏者) 録音:2015年10月31日、セント・ルークス・ジャーウッド・ホール(ライヴ録音) |
|
||
| LSO-5078(2CD) ★ |
LSOアメリカ・ライヴ ストラヴィンスキー:バレエ音楽「火の鳥」(1910年版) バルトーク:ピアノ協奏曲第3番 バレエ組曲「中国の不思議な役人」 プロコフィエフ:「ロミオとジュリエット」~モンタギュー家とキャピュレット家 |
イェフィム・ブロンフマン(P) ワレリー・ゲルギエフ (指)LSO 録音:2015年10月24日 ニュージャージー・パフォーミング&アーツセンター(ライヴ) |
|
||
| LSO-5083(2CD) ★ |
パガニーニ:24のカプリース(全曲) | ロマン・シモヴィ(Vn) 録音:2007年、セルビア |
|
||
| LSO-5090 |
LSOパーカッション・アンサンブルのジャズ スティーヴ・ライヒ:カルテット チック・コリア(キャリントン編):デュエット組曲 ジョー・ロック:Her Sanctuary 小曽根真(キャリントン編):Kato’s Revenge ギレルモ・シムコック:打楽器五重奏のための組曲 |
LSO パーカッション・アンサンブル、 ギレルモ・シムコック(P) 録音:2018年3月2、3、11日、2019年2月1-3日/ジャーウッド・ホール(セント・ルークス) |
|
||
| LSO-5092 |
パヌフニクの遺産III アヤンナ・ウィッター=ジョンソン:Fairtrade? エヴァン・キャンベル:Frail Skies セヴァンヌ・ホロックス=ホパイヤン:A Dancing Place (Scherzo) ドンフン・シン:In This Valley of Dying Stars アレックス・ロト:Bone Palace Ballet マシュー・サージェント:but today we collect ads パトリック・ジゲール:Revealing サーシャ・シーン:Ojos Del Cielo ベタン・モルガン=ウィリアムズ:Scoot マイケル・タプリン:Ebbing Tides ベンジャミン・アシュビー:Desires ジョアンナ・リー:Brixton Briefcase |
フランソワ・グザヴィエ=ロト(指)LSO 録音:2019年4月26,27日、ジャーウッド・ホール、セント・ルークス |
|
||
| LSO-5094(1SACD) |
ベートーヴェン:ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 op.61(カデンツァ:イェルク・ヴィトマン) ヴァイオリン協奏曲 ハ長調 WoO5~アレグロ・コン・ブリオ(断片) |
ヴェロニカ・エーベルレ(Vn/ストラディヴァリウス「ドラゴネッティ」(1700年製))
サー・サイモン・ラトル(指)LSO 録音:2022年3月11&12日、ジャーウッド・ホール、LSOセントルークス |
|
||
| LSO-5096(2SACD) |
ラトル~ストラヴィンスキー3大バレエ ストラヴィンスキー:「火の鳥」 「ペトルーシュカ」(1947年改訂版 ) 「春の祭典」(1947年改訂版) |
サー・サイモン・ラトル(指)LSO 録音:2017年9月21&24日バービカン・ホール、ロンドン (ラトルのLSO音楽監督就任記念演奏会シリーズ「This is Rattle」の演奏会の一環) |
|
||
| LSO-5122 |
OC-EAN FLOOR SUITE(海底の組曲) 1. 拍手 2. Unconditionally(絶対に)(ウィッター=ジョンソン作曲) 3. All Roads(ギレルモ・シンコック作曲) 4. チャリオット(ウィッター=ジョンソン、オフェイ・サキ作曲/シンコック編) 5. フォーリング(ウィッター=ジョンソン、アレックス・ウェブ作曲) 6. ホールディング(シンコック作曲) 7. Tidal Warning(ウィッター=ジョンソン作曲/LSO委嘱/世界初録音) 8. Ocean Floor Suite(海底の組曲)/ウィッター=ジョンソン作曲/LSO委嘱/世界初録音) 〔Prologue - The Darkest Hour - Pioneers - Ocean View〕 9. Forever(ウィッター=ジョンソン作曲) |
アヤナ・ウィッター=ジョンソン(声、チェロ、パーカッション、作曲) ギレルモ・シムコック(P、作曲) LSOパーカッション・アンサンブル〔ニール・パーシー、サム・ウォルトン、デイヴィッド・ジャクソン、ジェイコブ・ブラウン〕 録音:2022年11月12日、ジャーウッド・ホール(ライヴ録音) |
|
||
COpyright (C)2004 WAKUWAKUDO All Rights Reserved. |