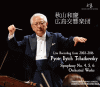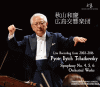 |
秋山和慶 |
| 広島交響楽団 |
|
|
東武レコーディングズ
TBRCD-0142(4CD)
税込定価
|
| 録音:2012年1月7日広島市文化交流会館 (YMFGもみじニューイヤーコンサート)
|
|
| 演奏時間: |
第1楽章 |
15:18 |
/ |
第2楽章 |
12:50 |
/ |
第3楽章 |
5:56 |
/ |
第4楽章 |
12:43 |
|
| カップリング/交響曲第4番、交響曲第6番「悲愴」、「白鳥の湖」(抜粋)、「エウゲニ・オネーギン」-ポロネーズ、「ロメオとジュリエット」、「フランチェスカ・ダ・リミニ」、組曲第4番-第3曲、弦楽セレナード、「フィレンツェの思い出」(弦楽合奏版)、デンマーク国家による祝典序曲
|
| “秋山の驚異的バランス感覚がもたらす安定感と感動!” |
東武レーベルから発売されている秋山&広島響コンピの録音を聴くにつけ、近年のピリオド奏法には目もくれない純音楽路線を愚直に直進する姿には敬服するばかりで、2025年は秋山氏の演奏会は片っ端から聴こうと決意していた矢先の訃報は、本当に痛恨の極みです。
秋山の指揮姿にも現れている端正な造形力と作品への敬意の払い方、作品そのものの魅力を過不足なく伝えるセンスは、まさに指揮者の鏡。この「チャイ5」においてもそのことを改めて再認識させられました。
第1楽章はやや遅めのテンポで、表情は常に伏し目がち。隠しきれない不安の敷き詰め方が実に絶妙です。第2楽章は大見得を切れるシーンもありますが、ただ素直にスコアを再現すればニュアンスが素直に立ち昇ることを実感。長年培ってきたバランス感覚一本で、作品にとって最適な表情がこれほど豊かに広がるのです。
バランス感覚といえば、終楽章主部冒頭!中庸以下のテンポを採用すると、指揮者に響きの重量感、凝縮感を操作できる力量が不足していることが露呈してしまうことが多いですが、ここでの秋山のバランス感覚は驚異的に素晴らしいので是非ご注目を。
秋山は作品の「らしさ」を直感的に捉える能力に人一倍長けている指揮者だと常々感じていましたが、この終楽章におけるスラブ的な雰囲気濃厚な動機を大斉奏するシーンでも、まさにその雰囲気を的確に表出。日本人らしい節度も交えた響きの説得力は、日本人のみならず世界中の音楽ファンが共鳴するはず。
ただ、唯一残念なのは録音のバランス。弦と金管が同時に鳴っている際に相対的に弦が弱く聞こえる場合がありますが、ホールの響きや構造によるものなのか、録音技師の問題なのでしょうか?
その関連で言えば、CD1に収録されている交響曲第4番と「白鳥の湖」はアーステールプラザ大ホールで収録されており、この響きが絶品!と同時に演奏が超名演奏で、特に「白鳥の湖」終曲の妥協のない表現の刻印ぶりは尋常ではなく、過去の名演を一気に吹き飛ばすこと必至!したがって、この大名演の併録をもって「特選」扱いとしたいと思います。【2025年4月・湧々堂】 |
|
| 第1楽章のツボ |
| ツボ1 |
中庸テンポで、暗さを強調することなきく淡々と進行。部分的に弦の響きが強すぎる箇所あり。
|
| ツボ2 |
遅すぎず速すぎず、楽想が伝わりやすい最適なテンポ。クラリネットとファゴットのブレンド感も良好。
|
| ツボ3 |
丁寧にスラーを実行。8分音符の下降でわずかにテンポを落とす
|
| ツボ4 |
スラーの8分音符は、テンポこそ落とさないが、先へ行くのをためらうような雰囲気が絶妙に漂う。。
|
| ツボ5 |
実に入念、かつ丁寧にフレージング。細かいスラーの指示の意図を汲みながらもそれに縛られない自然なフレージングにセンスを感じる。
|
| ツボ6 |
強弱の変化はぼかし気味。 |
| ツボ7 |
良く縦の線が揃っているがメカニックに陥らない。
|
| ツボ8 |
単に甘美なだけではなく、「ほのかな憧れ」を匂わせている。 |
| ツボ9 |
インテンポのまま。やや遅めのテンポを基調としていることで、細かい木管の動きが捉えられている。
|
| 第2楽章のツボ |
| ツボ10 |
冒頭の低弦は、比較的淡白な進行。ホルンは、ミスなく無難。その後のオーボエ、クラリネットは緊張気味。
|
| ツボ11 |
テンポはむしろ遅めに設定。 |
| ツボ12 |
テンポは変えない。クラリネットもファゴットもぎこちない。
|
| ツボ13 |
ヴァイオリンのピチカートがやや弱い気がする。
|
| ツボ14 |
大音量の縦割りの打ち込みに引っ張られず、水平なフレージングの佇まいを壊さないい配慮が息づいている。来れずまさに指揮者の力量!
|
| ツボ15 |
残響が多めなせいか、音の隈取が不明瞭。 |
| 第3楽章のツボ |
| ツボ16 |
わずかにテンポを落とす。 |
| ツボ17 |
全体のハーモニーの風合いを活かしながらの全声部の連携が絶妙。「鮮やかな連携プレー」ではない雰囲気の作り方に敬服。
|
| ツボ18 |
個々の奏者の技量不足で、一本のラインが築けていない。
|
| 第4楽章のツボ |
| ツボ19 |
テンポは標準的。声部バランスもニュアンスもすべてが中庸だが、凡庸さに傾かない職人芸が冴える。
|
| ツボ20 |
ホルンは脇役ではあるが、残響のせいか木管がやや遠くで響くので、結果的にホルンと木管は同等のバランスで響く。
|
| ツボ21 |
テンポは標準的なものよりよりやや遅め。ティンパニは、58,62小節の頭にアクセントあり。弦とともに見事な高揚感を作り出す。
|
| ツボ22 |
完全に無視。 |
| ツボ23 |
ごく標準的なバランス。 |
| ツボ24 |
主部冒頭よりやや早めのテンポのテンポ。 |
| ツボ25 |
意外にも剥き出しの強打だが、やや唐突感あり。
|
| ツボ26 |
主部冒頭のテンポ。手前の311小節で一瞬テンポを落とす。
|
| ツボ27 |
標準的なテンポ。直前からテンポを落とす。
|
| ツボ28 |
本来の音価よりも長め。 |
| ツボ29 |
重量感はないが堅実な進行。 |
| ツボ30 |
弦は音を切り、トランペットはレガート気味。 |
| ツボ31 |
改変なしだが、弦とのバランスを調整すれば、トランペットを全て主旋律に変更する必要などないことを実証。ただし、ここではホールの特性なども関係した偶然の産物である可能性もある。 |
| ツボ32 |
明瞭だが強靭さに欠ける。 |
| ツボ33 |
堂々たるインテンポ進行だが、管楽器の音の外しが興を削ぐ。 |