| 湧々堂HOME | 新譜速報: 交響曲 管弦楽曲 協奏曲 器楽曲 室内楽 声楽曲 オペラ バロック 廉価盤 シリーズもの マニア向け | |||
| 殿堂入り:交響曲 管弦楽 協奏曲 器楽曲 室内楽 声楽曲 オペラ バロック | SALE !! | レーベル・カタログ | チャイ5 | |
| 東武レコーディングズ・WEITBLICKセール |
| 特価受付期間~2025年12月20日まで !! |
| 品番 | 内容 | 演奏者 |
|---|---|---|
 TBRCD-0029(2CD) |
マガロフ~1991年4月12日ライヴ ラヴェル:クープランの墓 ベートーヴェン:ピアノ・ソナタ第23 番「熱情」 ショパン:24 の前奏曲Op.28 ワルツ第2 番変イ長調Op.34-1 夜想曲第20 番嬰ハ短調 練習曲ハ短調Op.10-12「革命」 |
ニキタ・マガロフ(P) 録音:1991 年4 月12 日東京・芸術劇場大ホール、ライヴ |
|
||
 TBRCD-0031(2CD) |
マガロフ~1991年4月14日ライヴ モーツァルト:ピアノ・ソナタ第3 番 スカルラッティ:ソナタL.33、L.361 ショパン:ピアノ・ソナタ第3 番 ムソルグスキー:組曲「展覧会の絵」 グリンカ(バラキレフ編):ひばり モーツァルト:トルコ行進曲 メンデルスゾーン:紡ぎ歌 |
ニキタ・マガロフ(P) 録音:1991 年4 月14 日東京・芸術劇場大ホール、ライヴ |
|
||
 TBRCD-0060(5CD) |
ベートーヴェン:交響曲全集 | エドゥアルド・チバス(指) ベネズエラSO カローラ・グレーザー(S),カティウスカ・ロドリゲス(Ms)、 イドヴェル・アルヴァレス(T),アンドレアス・ダウム(Br) テレサ・カレーノ・オペラ・コーラス、エミール・フリードマンcho、UC合唱団、ホセ・アンゲル・ラマスcho 録音:2005~2018 年ホセ・フェニックス・リバス ホールにおけるデジタル・ライヴ録音: 録音:2007年7月1日(交響曲第1番、第3番)、2018年3月17日(交響曲第2番、第4番)、2017年3月22日(交響曲第6番、第8番)、2005年3月16日(交響曲第5番)、2005年2月3日(交響曲第7番)、2008年4月24日(交響曲第9番) |
|
||
| TBRCD-0065(3CD) |
ブルックナー:後期三大交響曲集 交響曲第7番 交響曲第8番* 交響曲第9番# |
エドゥアルド・チバス(指) ベネズエラ交SO 録音:2004年5月27日、2005年11月10日*、2007年6月7日# ホセ・フェニックス・リバスホールにおけるデジタル・ライヴ録音 |
|
||
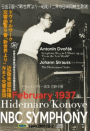 TBRCD-0112(1CD) |
「日出る国へ〝新世界〟~昭和十二年の日米同時生放送」
(1)ドヴォルザーク:交響曲第9番「新世界より」 (2)J・シュトラウス(近衞編):喜歌劇「こうもり」組曲 |
近衞秀麿(指)NBC響 録音:(1)1937年2月16日、(2)1937年2月14日,NBC8H スタジオ 音源提供:アメリカ議会図書館(Library of Congress) 協力:近衞音楽研究所、 ウィスコンシン歴史協会(Wisconsin Historical Society)、 NBC ユニヴァーサルLLC、Donald Meyer(Lake Forest college) |
|
||
 TBRCD-0134(5CD) |
ブリュッヘン/ベートーヴェン:交響曲全集 ■CD1 交響曲第1番 交響曲第3番「英雄」 ■CD2 交響曲第2番 交響曲第6番「田園」* ■CD3 交響曲第4番 交響曲第5番「運命」 ■CD4 交響曲第8番 交響曲第7番* ■CD5 交響曲第9番「合唱付き」 |
フランス・ブリュッヘン(指揮) 新日本フィルハーモニーSO 栗友会cho、リーサ・ラーション(S)、ウィルケ・テ・ブルメルストゥルーテ(A) 、ベンジャミン・ヒューレット(T)、デイヴィッド・ウィルソン=ジョンソン(Br) ■CD1 :録音:2011年2月8日すみだトリフォニーホール ■CD2 :録音:2011年2月8日すみだトリフォニーホール、2011年2月16 日すみだトリフォニーホール* ■CD3 :録音:2011年2月11日すみだトリフォニーホール ■CD4 :録音:2011年2月21日サントリーホール 、2011年2月16 日すみだトリフォニーホール* ■CD5:録音:2011年2月21日サントリーホール |
|
||
 TBRCD-0147(4CD) |
ブリュッヘン+新日本フィルの音楽遺産2 (1)ラモー:歌劇「ナイス」序曲とシャコンヌ (2)シューマン:交響曲第2番 (3)シューマン:交響曲第4番 (4)モーツァルト:交響曲第31番「パリ」(四楽章版) (5)シューベルト:交響曲第9番「ザ・グレート」 (6)ハイドン:交響曲第102番、 (7)ハイドン:交響曲第103番「太鼓連打」 (8)ハイドン:交響曲第104番「ロンドン」 (9)アンコール(ハイドン:交響曲第104番~第4楽章) |
フランス・ブリュッヘン(指) 新日本フィルハーモニーSO 録音:(1)(2)(4)2005年2月18日すみだトリフォニーホール(第381回定期演奏会) (3)2007年1月26日すみだトリフォニーホール(第412回定期演奏会) (5)2005年2月25日サントリーホール(第382回定期演奏会) (6)-(9)2009年2月28日すみだトリフォニーホール(ハイドン特別演奏会) |
|
||
 TBRCD-0151(4CD) |
近衞秀麿~京都大学SOとの歴史的名演集 ■CD1 (1)リスト:交響詩「前奏曲」 (2)ベートーヴェン:交響曲第2番(ステレオ収録) (3)ベートーヴェン:「レオノーレ」序曲第3番 (4)ヨゼフ・シュトラウス:ポルカ「村の鍛冶屋」 (6)ベートーヴェン:「レオノーレ」序曲第3番 ■CD2 (1)シューマン:交響曲第3番「ライン」 (2)ベートーヴェン:ピアノ協奏曲第3番 ■CD3 (1)モーツァルト:交響曲第41番「ジュピター」 (2)R・シュトラウス:管楽セレナード (3)グリーグ:二つの悲しい旋律 (4)マーラー:さすらふ若人の歌 (5)ワーグナー:歌劇「タンホイザー」序曲 ■CD4 (1)グリンカ:歌劇「ルスランとリュドミラ」序曲 (2)ドビュッシー:「小組曲」 (3)ブラームス:交響曲第1番 |
近衞秀麿(指) 京都大学SO ■CD1 録音:(1)1964年12月21日大阪公演 大阪サンケイホール (2)-(4)1964年12月16日京都公演・京都会館(ステレオ) (6)1964年12月21日大阪公演 大阪サンケイホール ■CD2 霧生トシ子(P) 録音:1968年12月9日大阪公演 大阪厚生年金会館中ホール ■CD3 録音:1970年12月21日大阪公演 大阪厚生年金会館大ホール 市来崎のり子(Ms) ■CD4 録音:1971年6月28日大阪公演 大阪厚生年金会館中ホール |
|
||
| TBRCD-0155 |
(1)ホルスト:組曲「惑星」 (2)モーツァルト:「フィガロの結婚」序曲 (3)モーツァルト:ホルン協奏曲第3番 |
森正(指)東京都SO (3)笠松長久(Hrn)、 (1)日本合唱協会(女声合唱) 録音:1982年8月5日新宿文化センター・ライヴ(第153 回ファミリーコンサート) |
|
||
| TBRCD-0156 |
ブルックナー:交響曲第4番「ロマンティック」(第1稿1874 年版) | 朝比奈千足(指)東京都SO 録音:1982年10月12日五反田簡易保険ホール・ライヴ(第1稿・日本初演ライヴ) |
|
||
 ERT-1039 |
グラズノフ:ヴァイオリン協奏曲 ブルッフ:ヴァイオリン協奏曲第1番 |
シルヴィア・マルコヴィチ(Vn) ミルツェア・クリテスク(指) ジョルジュ・エネスコPO 録音:1973 年9 月自由新聞社大理石ホール |
|
||
 ERT-1044(5CD) UHQCD |
ベートーヴェン:交響曲全集 (1)交響曲第1番/(2)交響曲第3番「英雄」 (3)交響曲第2番/(4)交響曲第6番「田園」 (5)交響曲第4番/(6)交響曲第5番「運命」 (7)「エグモント」序曲/(8)交響曲第8番 (9)交響曲第7番/(10)レオノーレ序曲第3番 (11)交響曲第9番「合唱」(ルーマニア語歌唱) (12)「コリオラン」序曲 |
ジョルジュ・ジョルジェスク(指) ブカレスト・ジョルジュ・エネスコPO エミリャ・ペトレスク(S),マルタ・ケスラー(Ms)、イオン・ピソ(T)、マリウス・リンツラー(Bs)、 ジョルジュ・エネスコ・フィルcho、ルーマニア放送cho 録音:(1)1961年5月、(2)1961年3月 (3)1961年4月20日、(4)1961年10月 (5)1962年1月、(6)1961年8月 (7)1962年1月11日、(8)1961年5月 (9)1962年1月、(10)1962年1月 (11)1961年7月、(12)1961年8月 全てルーマニア文化宮殿ホール(ステレオ) ※CD日本プレス。美麗夫婦箱5枚組。英語、日本語によるライナーノート付 |
|
||
 SSS-0098 |
ヨッフム&ベルリン・ドイツ響/1981ブラームス・プログラムVol.2 ブラームス:交響曲第1番 |
オイゲン・ヨッフム(指) ベルリン・ドイツSO(西ベルリン放送響) 録音:1981年6月7,8日 フィルハーモニー・ベルリン・ライヴ、ステレオ・ライヴ |
|
||
| SSS-0199 |
チャイコフスキー:交響曲第4番、 ビゼー:交響曲第1番 |
ジョルジュ・プレートル(指) シュトゥットガルトRSO 録音:1991年6月28日リーダーハレ |
|
||
| SSS-0210(2CD) |
イダ・ヘンデル、ストックホルム・リサイタル
ベートーヴェン:ヴァイオリン・ソナタ第7 番 バッハ:無伴奏ヴァイオリン・パルティータ第2 番 BWV1004~「シャコンヌ」 オットー・オルソン:ヴァイオリン・ソナタ第2 番 サン=サーンス:序奏とロンド・カプリチオーソ ブラームス:ハンガリー舞曲第5番 ラヴェル:ハバネラ形式の商品 リムスキー=コルサコフ:熊蜂の飛行 |
イダ・ヘンデル(Vn) クレイグ・シェパード(P) 録音:1984 年12 月9 日ベルワルドホール・ライヴ(ステレオ) (音源提供:スウェーデン放送協会) |
|
||
 SSS-0212 |
初出!ヨアンナ・マルツィ /1976年のステレオ・スタジオ録音 バルトーク:ヴァイオリンとピアノのためのラプソディ第1 番 モーツァルト:ヴァイオリン・ソナタ第 24 番ヘ長調K.376(374d) シューベルト:ヴァイオリンとピアノの二重奏曲D.574「デュオ・ソナタ」 |
ヨアンナ・マルツィ(Vn) イシュトヴァン・ハイジュ(P) 録音:1976 年11 月30 日チューリヒ・放送スタジオ2、スタジオ録音 (音源提供:スイス放送) |
|
||
 SSS-0213(2CD) |
エディト・パイネマン~WDRリサイタル録音集 ベートーヴェン:ヴァイオリン・ソナタ第7番ハ短調op.30-2 モーツァルト:ヴァイオリン・ソナタ第27番ト長調K.379 シューベルト:ヴァイオリン・ソナタ第3番ト短調D..408* ブラームス:FAEソナタよりスケルツォハ短調* ベートーヴェン:ヴァイオリン・ソナタ第2番イ短調Op12-2# シューベルト:幻想曲ハ長調D.934## |
エディト・パイネマン(Vn) ヘルムート・バース(P) イェルク・デムス(P)*,# ロバート・アレクサンダー・ボーンク(P)## 録音:1967年10月4日、1966年6月24日*、4月26日#、1957年6月23日## 音源提供:WDRケルン放送(モノラル) |
|
||
| SSS-0226 |
ドビュッシー:交響詩「海」 ヒンデミット:室内音楽第1 番Op.24-1 マーラー:交響曲第10 番「アダージョ」 |
ブルーノ・マデルナ(指) ハーグ・レジテンティO(ハーグPO) 録音:1972 年 2 月 24 日フィールゼン、フェストハレ、ステレオ・ライヴ |
|
||
 SSS-0228(3CD) |
エディト・パイネマン~SFB(ベルリン)未発表録音集 (1)シューマン:ヴァイオリン・ソナタ第1 番イ短調Op.105 (2)ブラームス:ヴァイオリン・ソナタ第2 番イ長調Op.100 (3)シューベルト:ヴァイオリン・ソナティナ第3番ト短調D.408 (4)スーク:ヴァイオリンとピアノのための4 つの組曲Op.17 (5)ベートーヴェン:ヴァイオリン・ソナタ第4 番イ短調Op.23 (6)シューベルト:ヴァイオリンと弦楽合奏のためのロンドイ長調(ピア ノ伴奏版)D.438 (7)ドヴォルザーク:4つのロマンティックな組曲Op.75 (8)モーツァルト:ヴァイオリン・ソナタ変ロ長調K.454 (9)シューベルト:幻想曲ハ長調D.934 |
エディト・パイネマン(Vn) (1)-(5)ヘルムート・バース(P)、 (6)-(9)レナード・ホカンソン(P) 録音:(1)-(3)1970年11月5日、(4)(5)1982年6月22日、(6)-(9)1987年5月19日、21日、いずれもSFBザール3,ベルリン(未発表スタジオ録音) |
|
||
| SSS-0232 |
フィルクスニー/ベルン・リサイタル1976年3月16日 モーツァルト:デュポールのメヌエットによる9つの変奏曲K.573 ショパン:ピアノ・ソナタ第3番 ロ短調Op.58 ヤナーチェク:「草陰の小道にて」第2集 ドヴォルザーク:主題と変奏Op.36 スメタナ:チェコ舞曲より「熊」 |
ルドルフ・フィルクスニー(P) 録音:1976年3月16日ベルン、放送スタジオ、ライヴ |
|
||
 SSS-0242(3CD) ★ |
レーグナー/シューベルト秘蔵名演集 (1)交響曲第2番変ロ長調D.125 (2)交響曲第6番ハ長調D.589 (3)交響曲第8番「未完成」 (4)交響曲第9番「ザ・グレート」 (5)序曲ニ長調D.556/(6)序曲ホ短調D.648 (7)序曲変ロ長調D.470 (8)5 つのメヌエットと5つのドイツ舞曲(弦楽合奏版)D.89 (9)6つのドイツ舞曲D.820(ウェーベルン編) |
ハインツ・レーグナー(指) ベルリンRSO 録音:(1)1978年9月24日ベルリンドイツ民主共和国宮殿ライヴ (2)1973年10月16,17日ベルリン放送大ホール1スタジオ録音 (3)1991年11月10日ベルリン・シャウシュピールハウス(現コンツェルトハウス)、ライヴ (4)1978年1月28日ベルリンドイツ民主共和国宮殿ライヴ (5)1973年12月10日ベルリン放送大ホール1スタジオ録音) (6)1973年9月28日ベルリン放送大ホール1スタジオ録音) (7)1973年10月15日ベルリン放送大ホール1スタジオ録音) (8)1973年12月11,12日ベルリン放送大ホール1スタジオ録音 (9)1990 年5 月27 日ベルリン・シャウシュピールハウス(現コンツェルトハウス)、ライヴ |
|
||
 SSS-0245(4CD) |
カイルベルト+ケルン放送響/初出スタジオ録音集1952-63 (1)モーツァルト:交響曲第30番 (2)モーツァルト:協奏交響曲変ホ長調 K.364/320d (3)モーツァルト:交響曲第40番 (4)ベートーヴェン:交響曲第4番 (5)シューマン:交響曲第4番 (6)ベートーヴェン:交響曲第9番「合唱」 (7)ブルックナー:交響曲第6番 |
ヨーゼフ・カイルベルト(指)ケルンRSO (2)ウィルヘルム・マイヤー(Ob) パウル・ブレシャー(Cl) ゲアハルト・ブルダック(Hrn) カール・ヴァイス(Fg) (6)ヴィルマ・リップ(S) ルクレツィア・ウェスト(A) エルンスト・ヘフリガー(T) ゴットロブ・フリック(Bs) ケルン放送cho 録音:(1)-(3)1957年9月14日、(4)1958年12月8日、(5)1952年6月6日、(6)1963年6月28日 以上、ケルン放送クラウス・フォン・ビスマルクザール(モノラル) |
|
||
Copyright (C)2004 WAKUWAKUDO All Rights Reserved. |